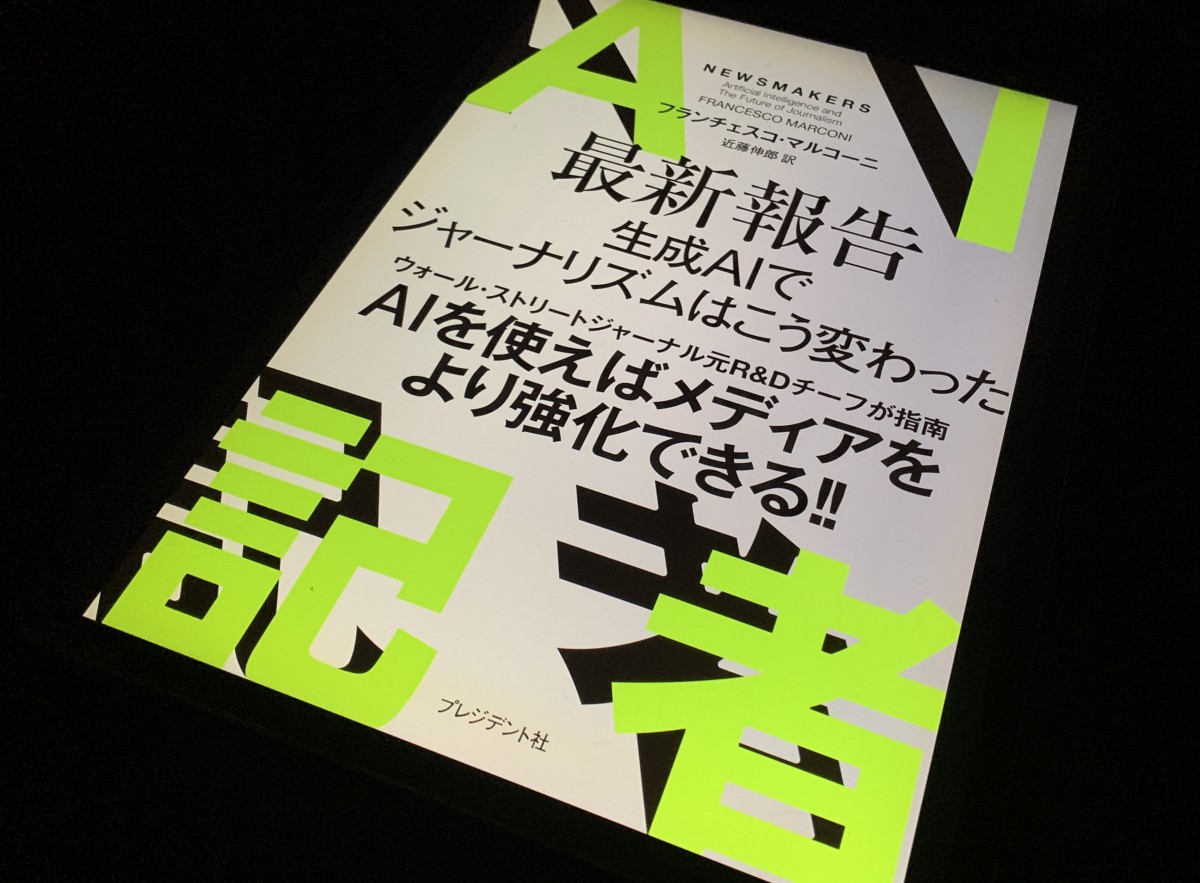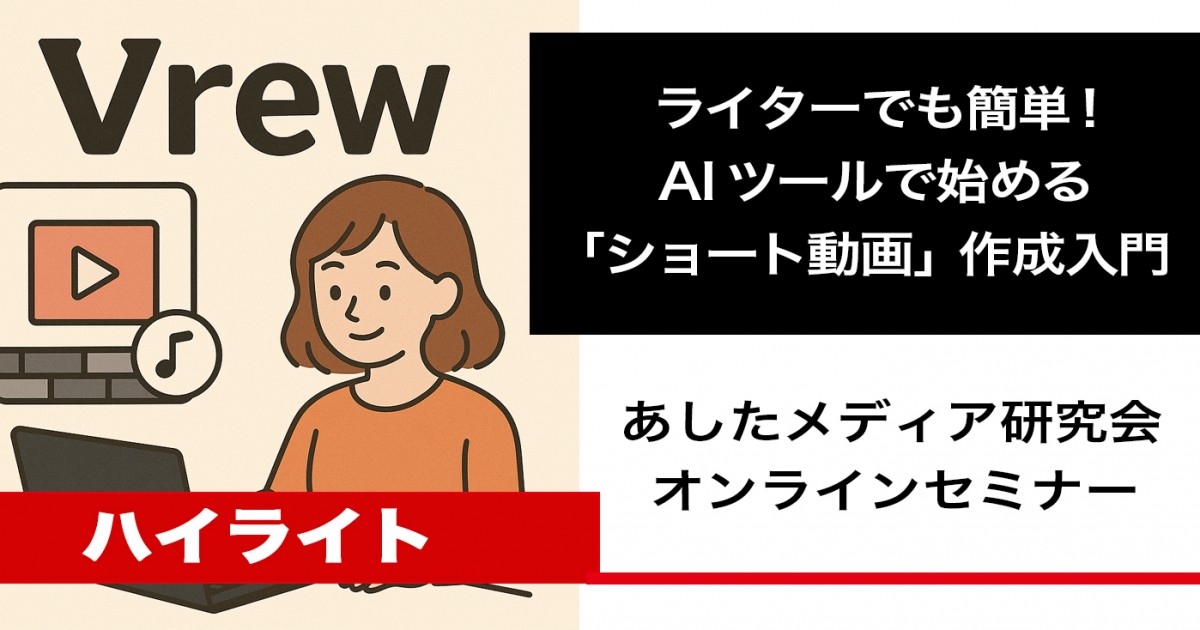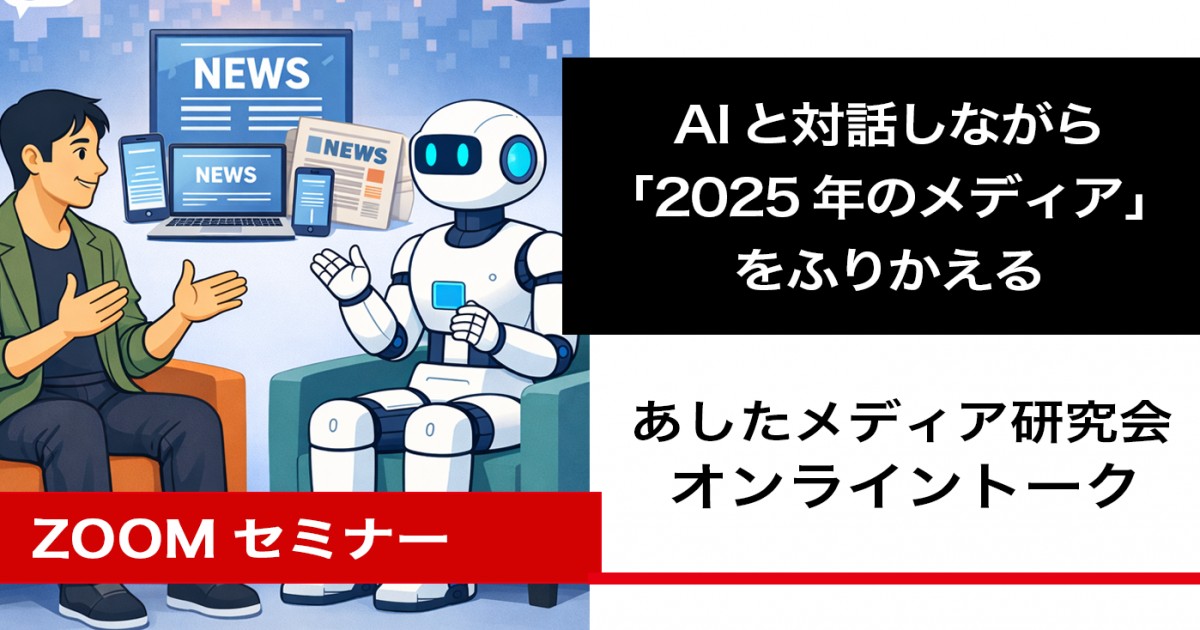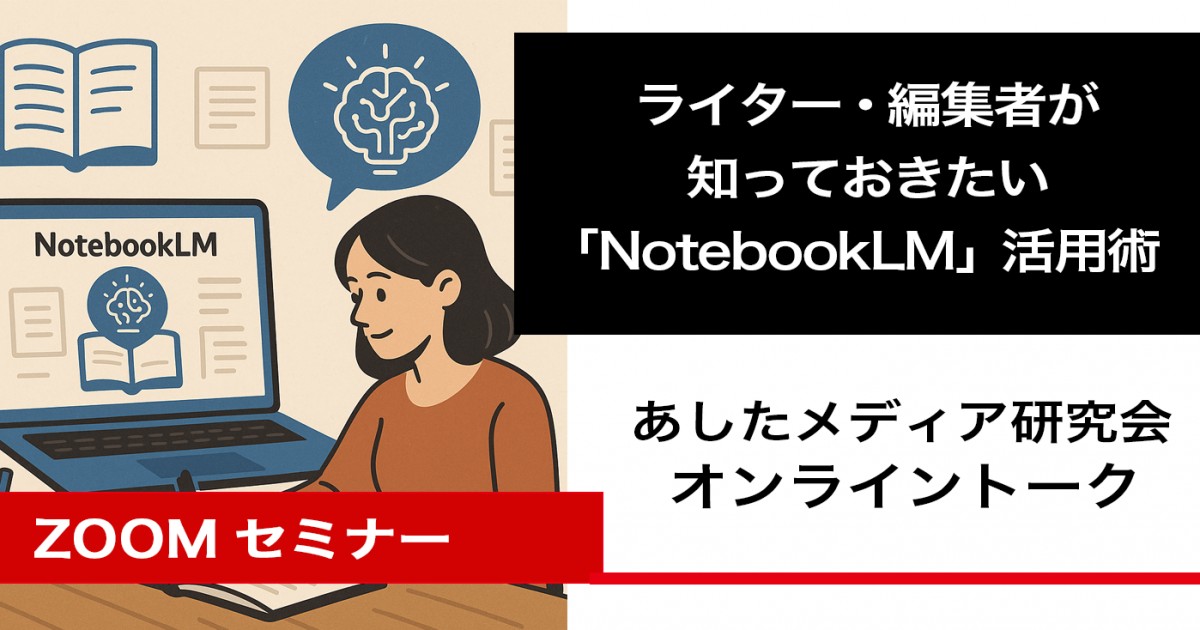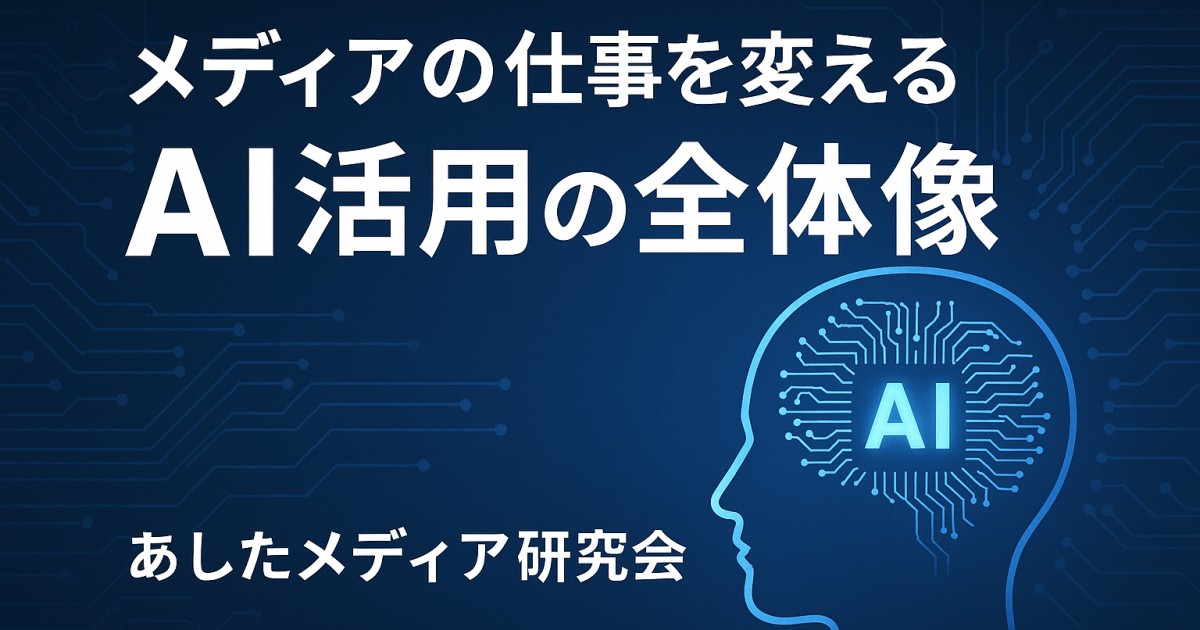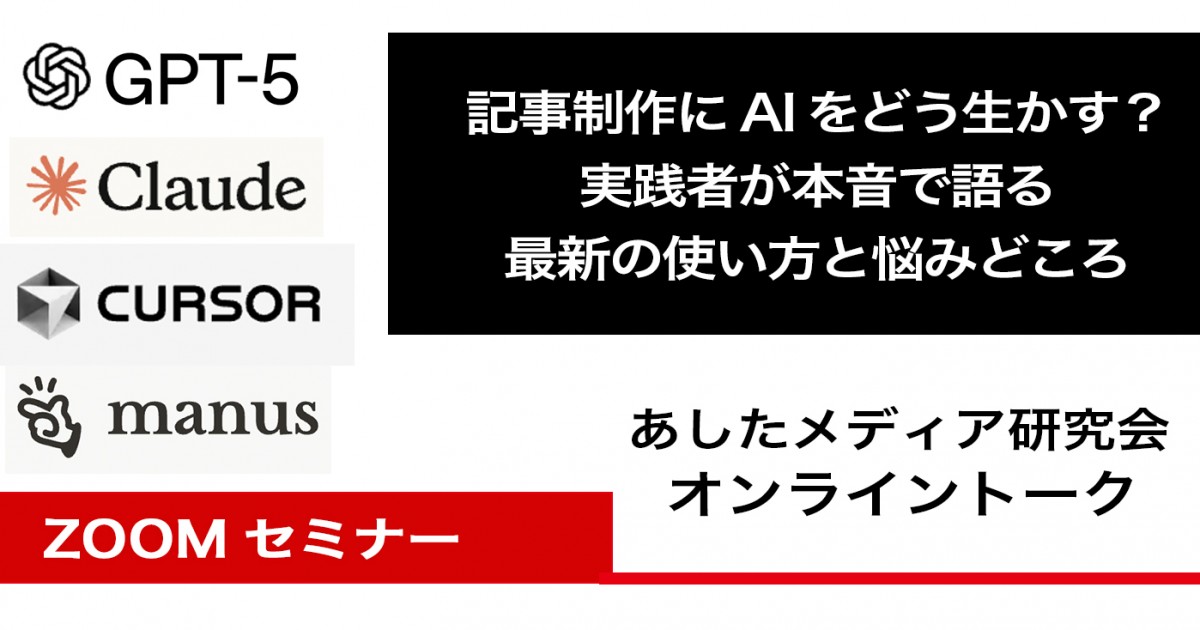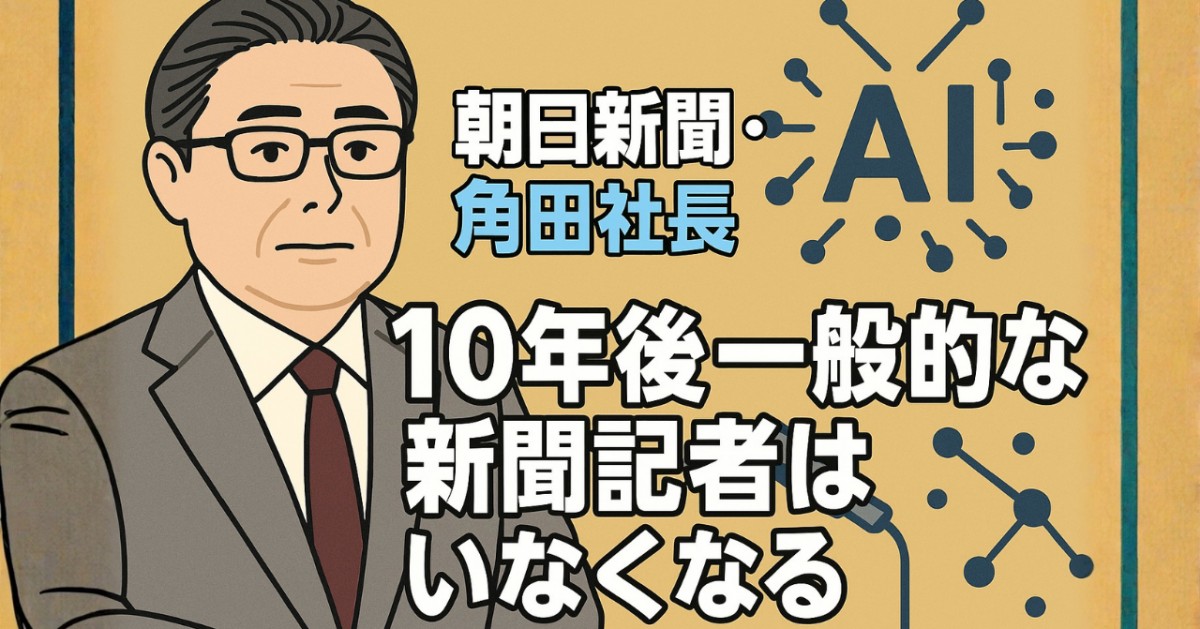AIは記者を「殺す」のか「育てる」のか?「AI記者」が投げかける問い
山田:著者はフランチェスコ・マルコーニさんで、AP通信やウォール・ストリート・ジャーナルで新規事業開発に携わってきた方です。AIの登場を受けて、メディアはどう変わっていくべきかについて論じた本です。
――タイトルを見ると「AIに記者が取って代わられるのでは?」と思ってしまいますが、実際にはどうなのでしょうか。
山田:内容は少し違っていて、「記者がAIをどう使いこなすか」が主なテーマです。たとえば「イテレーティブ・ジャーナリズム(反復型ジャーナリズム)」という言葉が出てきます。これは、新しい技術を使って、読者のニーズにリアルタイムで反応していくようなジャーナリズムの在り方を指しています。
――新聞やテレビなど、いわゆる既存メディアの現場では、AIに対する反発もあるように感じます。
山田:AIへの批判的な声はメディア業界に存在すると思いますし、私自身も当初は不安を感じていた時期がありました。しかしこの本では、AIというのは"点"を示す存在だと書かれています。たとえば、私たちが「これについて知りたい」と思ったとき、AIに聞くと、ネット上から詳しい情報を拾ってきて教えてくれる。それは本当に能力が高くて優れた面だと思いますし、活用しない手はないと感じます。
ただし、それはあくまでも"点"なんですね。一つひとつの事象を、何と結びつけるのか、どう切り取って伝えるのか。つまり"点"と"点"をつなぐのは、記者にしかできない仕事だということが強調されています。
――AIと人間がそれぞれ得意な部分を生かしていけばいい、という考え方ですかね。
山田:そうですね。記者はAIをうまく使いこなすことで、これまで以上の取材や報道ができるようになる。そういう使い方ができる記者になれるか、という視点がこの本にはあります。
――実際のメディアでの導入事例も紹介されていますか?
山田:AP通信では、金融ニュースの自動化を行っていて、それによって記者の作業時間が20%削減されたと書かれていました。その分、記者は教育や没入型のメディア制作に力を入れることができたそうです。
記者クラブの「紙文化」を変えたい
――山田さん自身は、記者クラブのDXに取り組んでいますね。詳しい内容は、あしたメディア研究会のオンラインセミナーで説明してもらいました。
山田:はい。現在開発中の「記者クラブDXシステム」は、全国の記者クラブに届く報道資料をデータベース化して共有できるようにしよう、という取り組みです。今も多くの記者クラブでは、A4用紙に印字された紙の資料が配布されています。手書きの予約票で受け付けている記者クラブもあるほどです。
私はテレビ局で記者をしていたとき、報道資料を受け取る側でしたが、記者からは「毎日何十枚も受け取って大変だ」という声を聞きます。一方で、その中にはすごく重要な情報もある。そうした「原石」がもっと多くのメディアに届くような仕組みをつくりたいと考えています。
――開発の背景には、地方ジャーナリズムへの課題意識もあるとか。
山田:たとえば、地元でパン屋さんがオープンしたとか、小学校で事故があったとか、病院が移転するといった話題は、そのエリアの人にとって大きなニュースです。でも、最近は記者の業務量が増えたこともあり、地域の取材が不十分になりがちで、地域の情報が地域で消費されなくなってしまう傾向があります。私は「情報の地産地消」が難しくなっている状態だと感じています。
――その背景には、記者クラブをめぐる厳しい現実もあるようですね。
山田:私たちが行った調査では、「この5年間で記者クラブを訪れる記者が減った」と感じている自治体職員が42.8%いました。記者が1人で多くの自治体を担当するようになって、取材の頻度が減っているという声が多かったです。背景には、メディアの人手不足や経営面の課題もあると思います。
――だからこそ、記者の力をより本質的な部分に集中させたいと。
山田:そうですね。一次情報に誰もがアクセスできるようになった今、記者はただ一次情報を記事にするだけでなく、ニュースを深掘りしたり、一次情報にもならない事実を掘り起こしたりすることが、以前よりも問われています。記者にしかできないことに注力してもらえるように、DXシステムを作っていきたいと考えています。
※この記事は、あしたメディア研究会のポッドキャスト「メディアびとブックトーク」の内容をもとに作成しました。
すでに登録済みの方は こちら