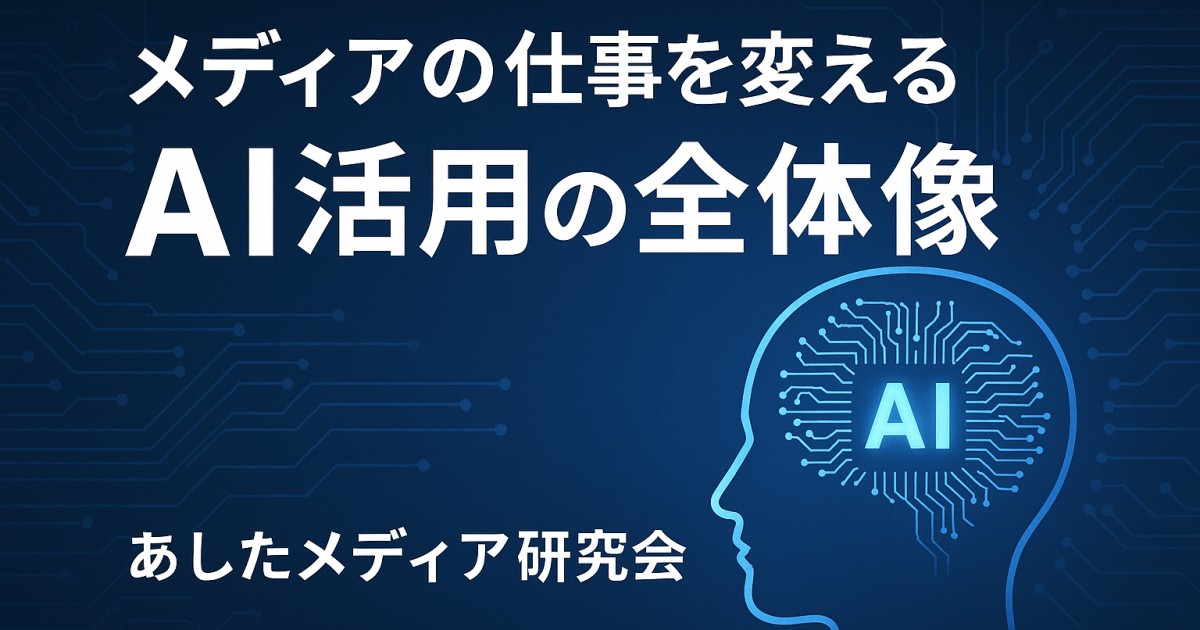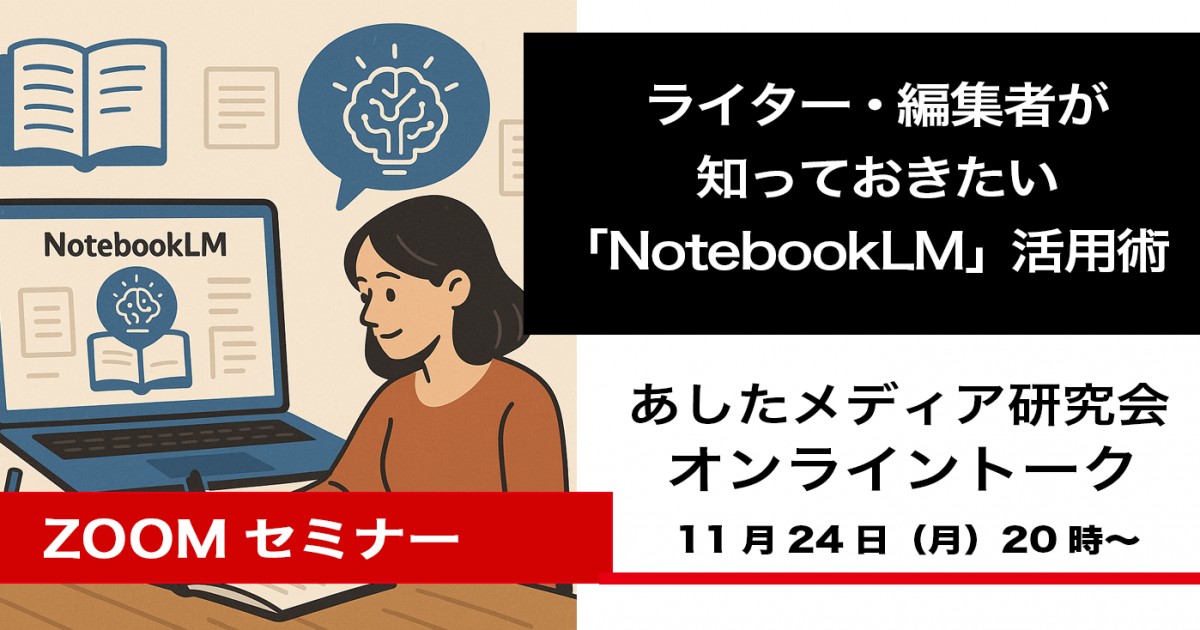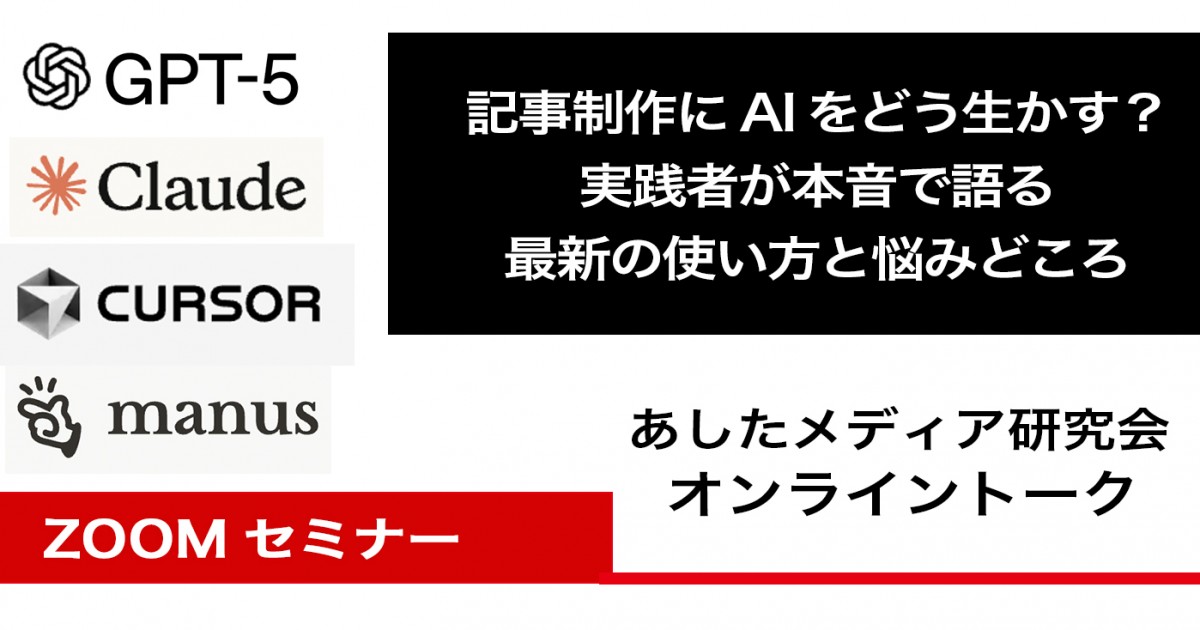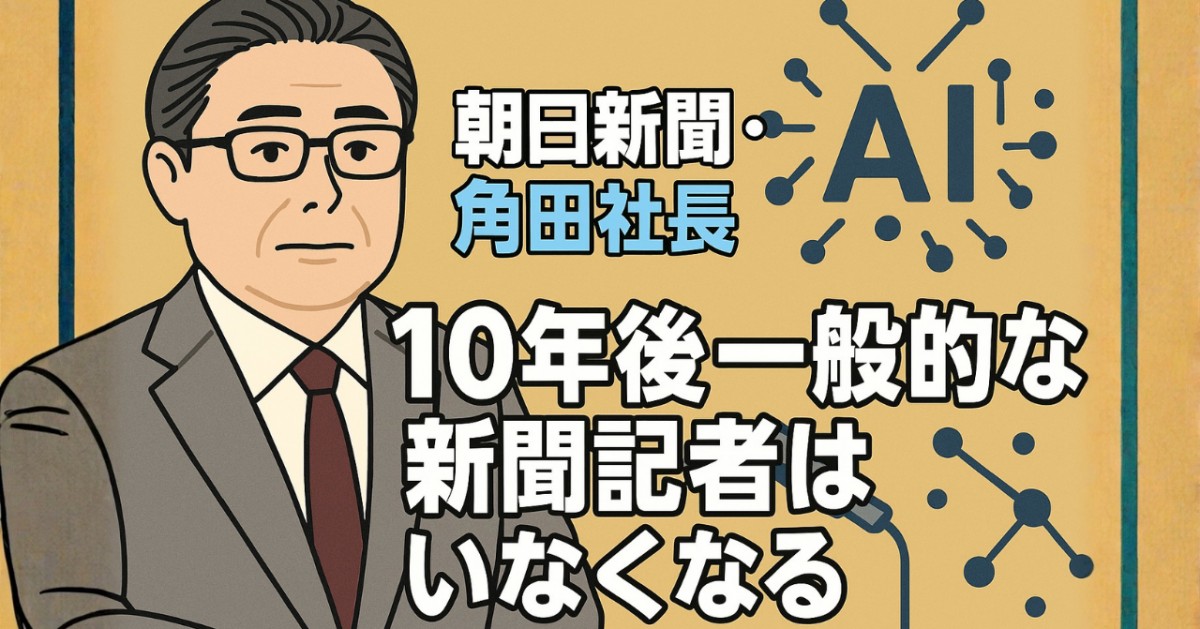「人生は踊り続けること」苦学生だった起業家を支える「村上春樹のメッセージ」

1年に1、2回は読み返す「人生のチューニング本」
――『ダンス・ダンス・ダンス』は1988年に出版された小説ですね。
濱本:私は1992年生まれですが、『ダンス・ダンス・ダンス』はその4年前に世に出た本ですね。村上春樹の初期三部作(『風の歌を聴け』『1973年のピンボール』『羊をめぐる冒険』)の続編にあたる長編小説。初めて読んだのは、大学を卒業して、社会人になったばかりのころです。
――どんなところに惹かれたのでしょう?
濱本:いわゆる「喪失と再生の物語」だと思うんですが、自分と重ね合わせて読んでいました。主人公は最初から何かを持っている恵まれた人物ではなくて、何かをつかんでも指の隙間からこぼれ落ちていくような人生を送っている。私も大学時代は苦学生で、バイト漬けの日々を送っていて、勉強の時間を取るのが大変でした。そんな自分にコンプレックスを持っていて、主人公に共感する部分があったんです。
――そんな一面があったんですね。
濱本:いま私がいるスタートアップの世界を見ると、実家が裕福で学生時代にバイトをする必要がなかったり、親が実業家で周りに経営者がいるのが当たり前だったりした起業家が大勢います。それに比べると、何も持っていない自分は無価値な人間じゃないかと思ってしまうこともあったんですよね。
――『ダンス・ダンス・ダンス』の中で、特に印象的なシーンはありますか?
濱本:主人公が「音楽が鳴っている間はとにかく踊り続けるんだ」というアドバイスを受ける場面があるんですが、それが胸に響きました。スタートアップでは「結果を出すことが全て」という価値観に支配されがちですが、この本を読んで、プロセスや変化そのものを楽しんでいけばいいんだ、と心が軽くなりました。いまも年に1~2回は読み返して、自分の考え方を整えています。いわば、人生の“チューニング”本です。
――もともと小説をよく読んでいたんですか?
濱本:学生のころは、もっぱら起業家の伝記ばかり読んでいました(笑)。小説を本格的に読むようになったのは、社会人になってから。『ダンス・ダンス・ダンス』は、ビジネス書では得られない「人生の伴走者」となる言葉をくれた一冊です。
ライターや編集者はすごく面白い知識を持っている
――そんな濱本さんが運営しているのが「theLetter」ですね。あしたメディア研究会でも利用させてもらっていますが、どんな発想から始めたのでしょうか?
濱本:theLetter は、書き手と読者を直接つなぐ、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。出版など従来のメディア業界が縮小していく中で、「数百人や数千人しか必要としていないけれど、その人たちにはものすごく価値がある情報」を継続的に届けられる仕組みを作りたいと考えました。
――なぜ「ニュースレター」という形式に注目したのですか?
濱本:読者と“直接つながれる”メディアだからです。SNSや検索アルゴリズムに依存しない、自立した発信手段。英語圏ではSubstackなどが成功していますが、日本でも必ずニーズがあると考えています。
――現在の「theLetter」の状況は?
濱本:昨年、黒字化を達成し、順調に成長しています。読者アカウントも数十万規模に増えました。書き手はジャーナリスト、大学教授、医師、弁護士など多彩です。最近では大手メディアとの連携も進み、プラットフォームとしての認知も高まっています。
――今後の展開については、どう考えていますか?
濱本:テキストだけでなく、音声や動画なども視野に入れています。「数百人、数千人のための、専門性のある発信」をどんなフォーマットでも可能にしていきたい。情報の“ロングテール”こそが、これからの時代に必要な価値だと思っています。
――メディア関係者に向けて、メッセージをお願いします。
濱本:ライターや編集者の人たちって、実はめちゃくちゃ面白い知識や教養を持っている人たちなんですよ。だからこそ、ニュースレターはもちろん、ポッドキャストや動画でもいいので、自分の知見をどんどん発信していってほしいですね。
※この記事は、あしたメディア研究会のポッドキャスト「メディアびとブックトーク」の内容をもとに作成しました。
すでに登録済みの方は こちら