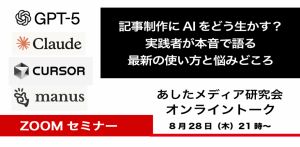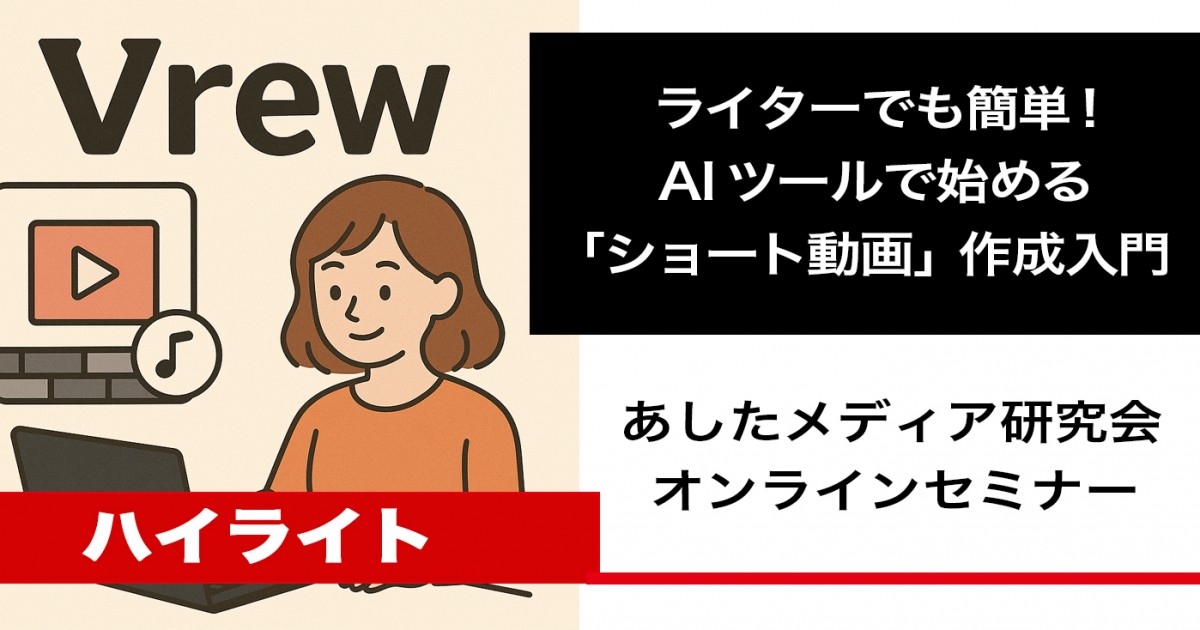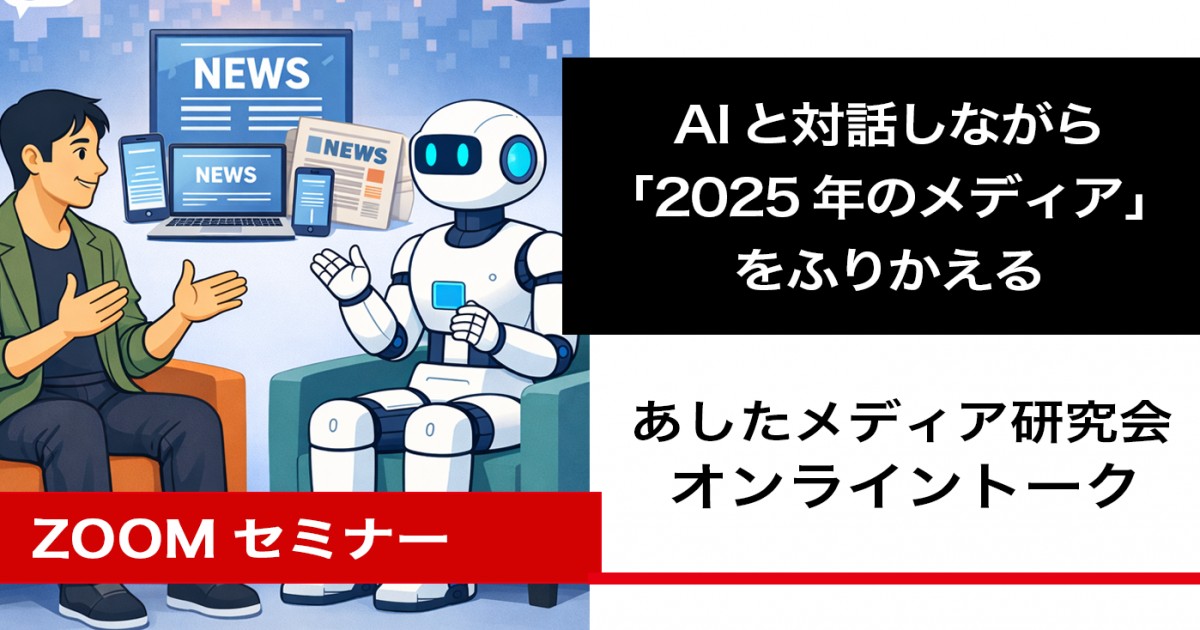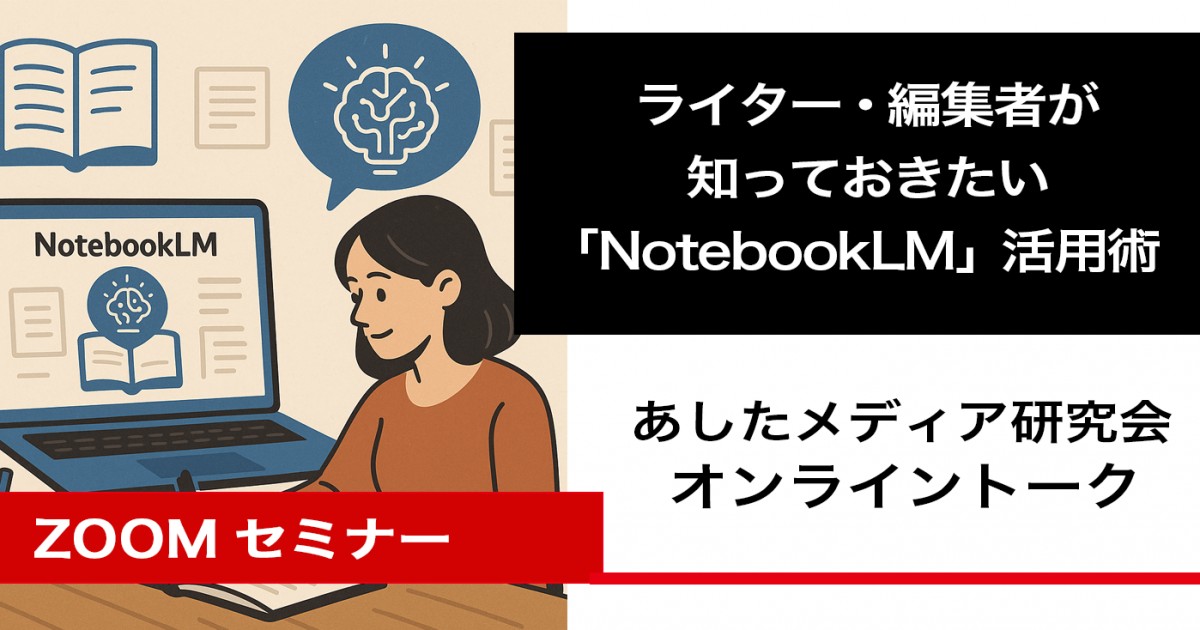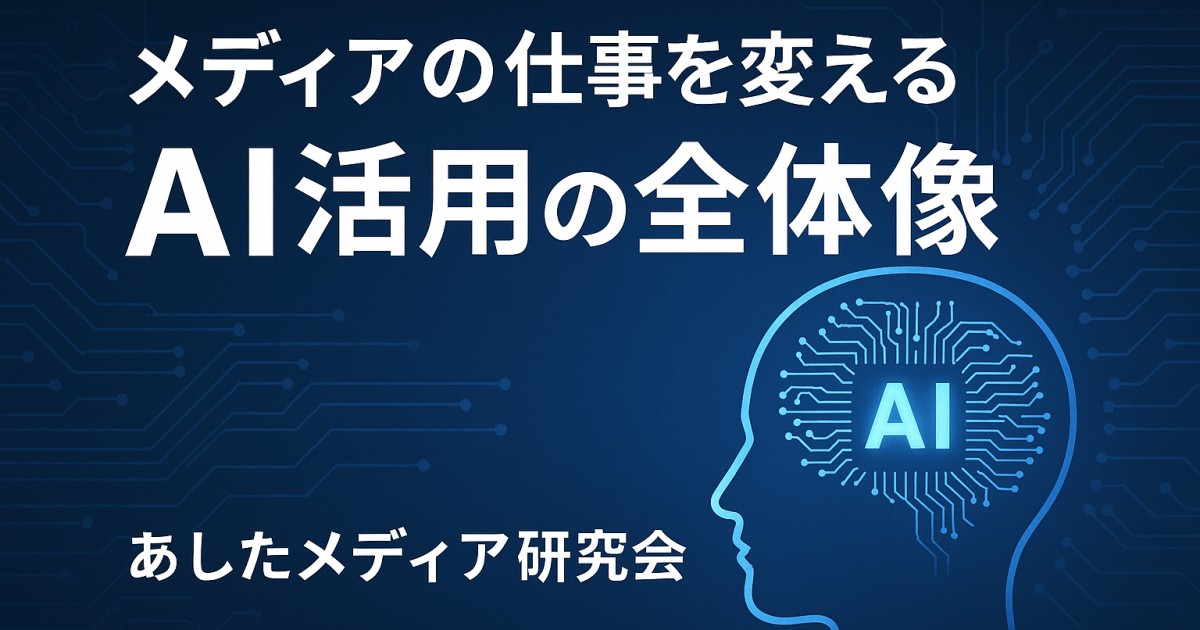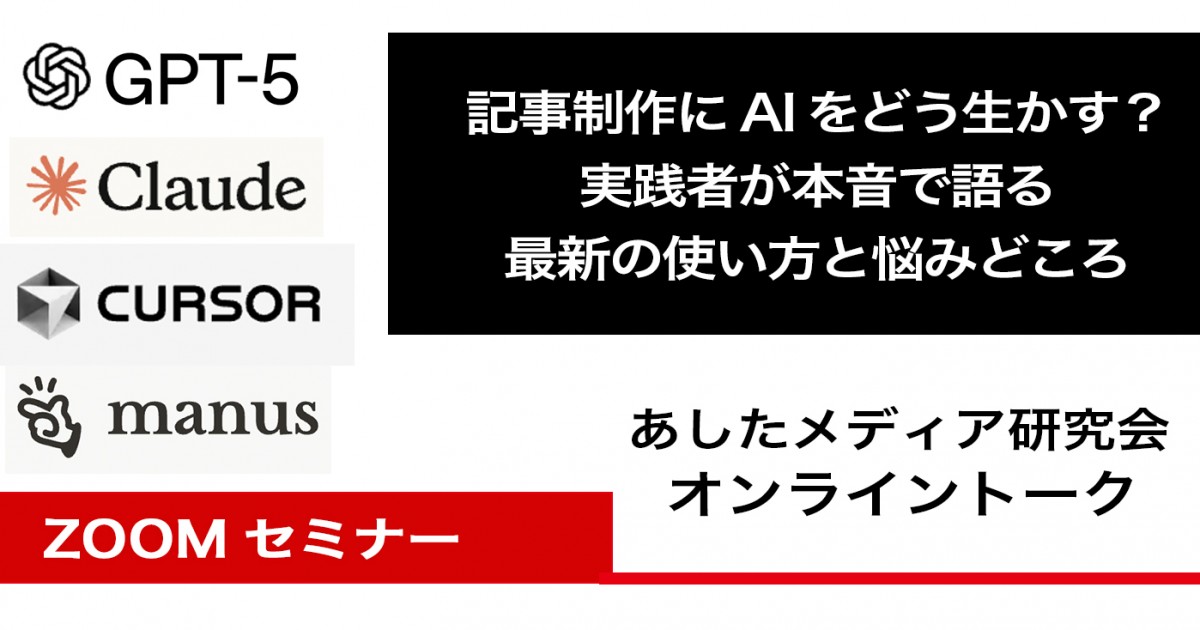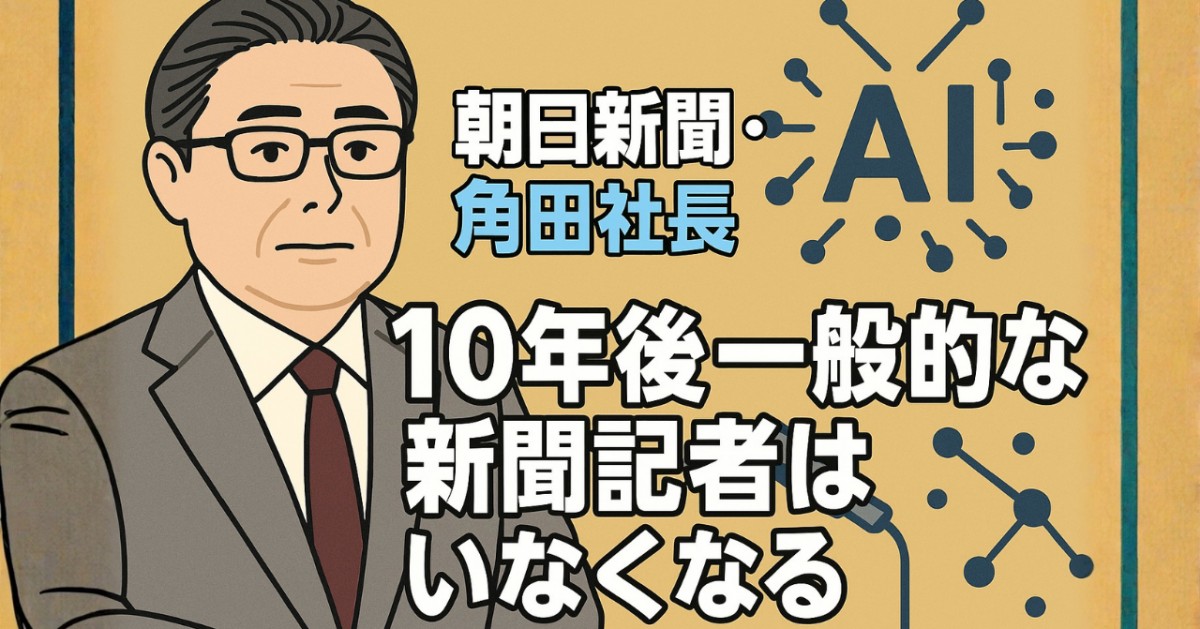AIは"ライター"、自分は"編集者"――インタビュー記事制作での実践的な使い方

ここで語られている内容は、あしたメディア研究会代表の亀松太郎が運営するニュースレターやウェブメディア「DANRO」のために、インタビュー記事を制作するシーンを想定しています。
この記事も、生成AIをフル活用して制作しました。AIがインタビューアーとなって、話し手(亀松)にインタビューした内容をもとに、AI自身が構成を考え、原稿を執筆しました。
本日8月28日(木)21時から、「記事制作とAI活用」をテーマにしたオンライントークイベントを開催します。
イベントの中では、このインタビュー記事をどのようにして制作したのか、その全プロセスをお伝えする予定です。
企画・質問づくり
Q:インタビュー記事で、最初にAIをどう使いますか?
A: まず企画や質問内容をざっくり出す作業をAIに手伝ってもらいます。私はChatGPTを使うことが多く、「誰に、どんなテーマで聞くのか」を与えて質問のたたき台を出してもらいます。
Q:質問設計の前提として、相手のリサーチはどうしていますか?
A: 相手についての調査・リサーチが必要なので、私はPerplexityを使っています。ウェブにある情報をまとめ、参照元リンクも付くので、気になった点は実際の参照元ページを開いて詳しく確認します。
収録と文字起こし
Q:実際の取材・インタビュー時に使うツールは?
A: 文字起こしツールを複数活用しています。主に使っているのは、NottaとLINEのWorks MobileのAI Noteです。オンライン取材の場合はZoomで行うことが多く、Zoom自体の文字起こし機能も利用します。
さらに最近は、Googleのスマートフォン「Pixel」シリーズも使っています。このPixelはスマホ端末内にAIが搭載されていて、インターネットに接続しなくてもリアルタイムで文字起こしができるのが特徴です。電波状況に左右されず、その場で文字に起こしてくれる安定感が非常に優れていると感じています。私はその用途のために中古のPixel端末を購入しました。
Q:Zoomの文字起こしを高く評価している理由は?
この記事は無料で続きを読めます
- 要約・整理
- 初稿生成とパターン比較
- ツールの使い分け
- 人間の編集と最終仕上げ
- 事実確認(ファクトチェック)
- タイトル・小見出し
- まとめ
すでに登録された方はこちら