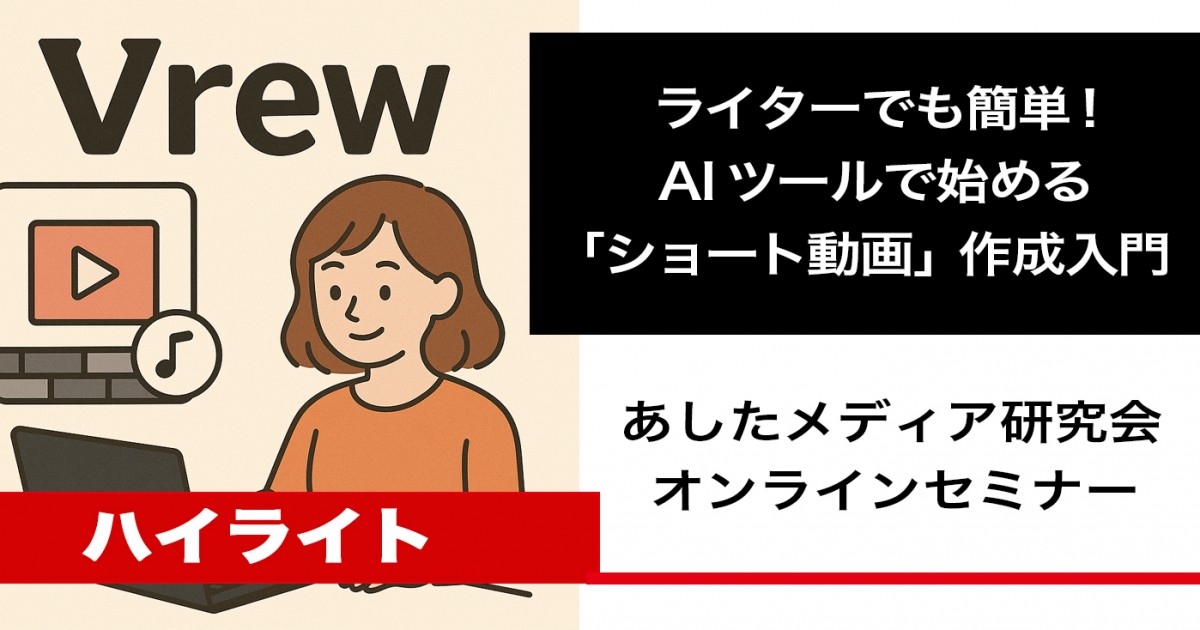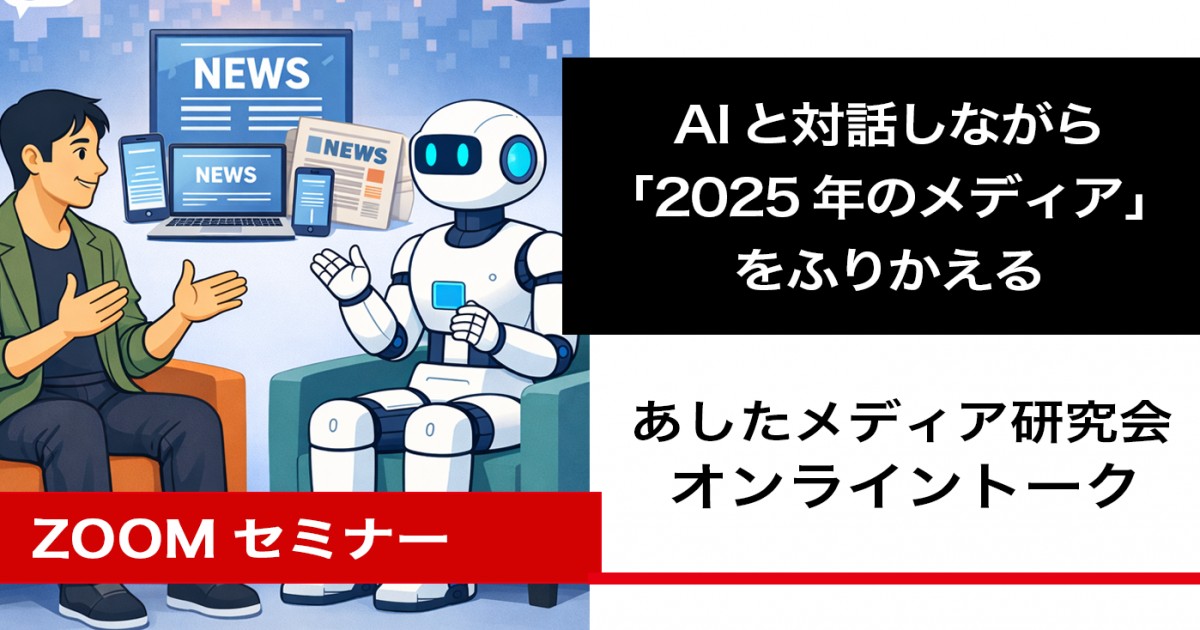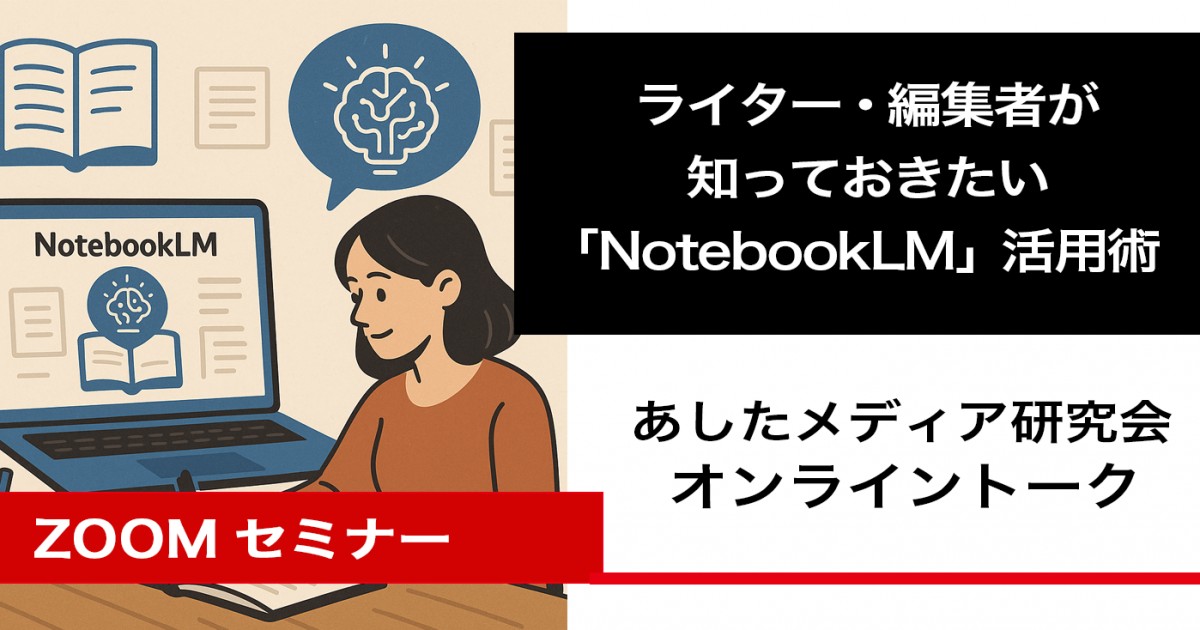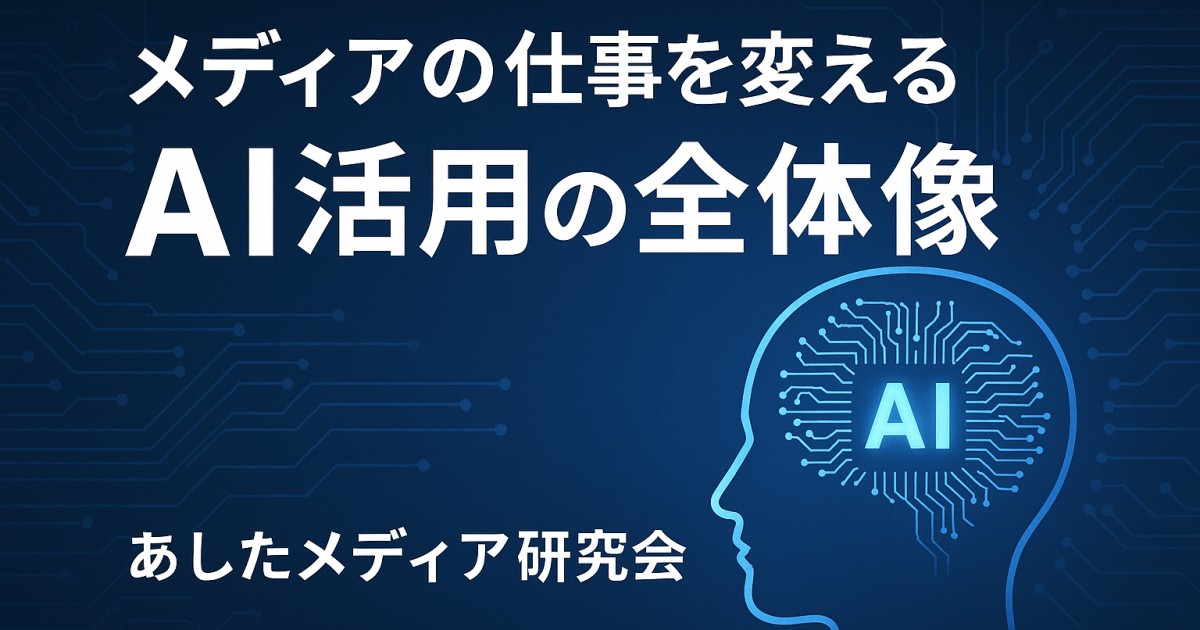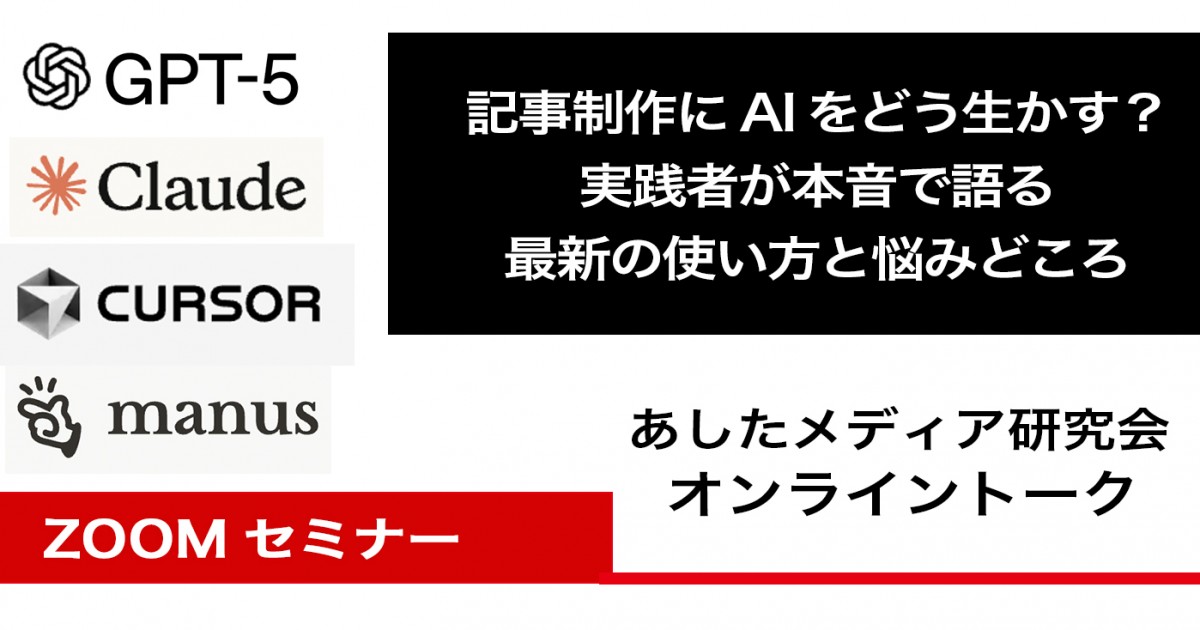朝日新聞・角田社長「10年後、一般的な新聞記者はいなくなる」 AI時代の新聞社はどうあるべき?
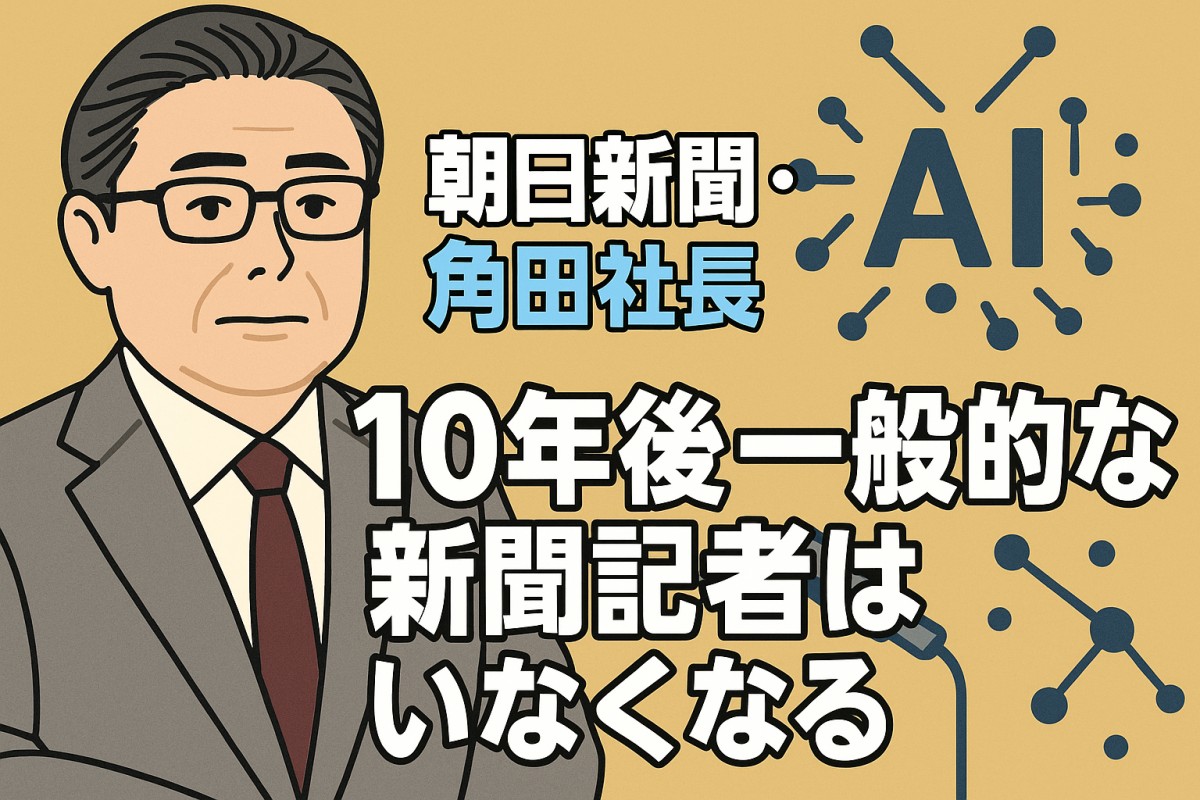
AI編集支援ツールを開発するスタートアップ「StoryHub」が10月30日、東京都内で「生成AI時代の編集革命」と題したイベントを開催しました。そのセッションの一つに朝日新聞社の角田社長が登壇し、AI時代の新聞社はどうあるべきかという展望を語りました。
今回、角田社長のセッションを聴講したのですが、そのときの「メモ」をもとに、AI音声によるポッドキャストを作成してみました。具体的には、Googleの生成AIツール「NotebookLM」にメモのデータを渡して、約18分のラジオ風トークのポッドキャストを作ってもらいました。
AIツールについて「勘違い」したAI
こちらがそのポッドキャストですが、実際に聴いてもらうとわかるように、「角田(つのだ)社長」を「かどたしゃちょう」、「DeNA」を「でぃーな」と読むなど、おかしな発音をしている箇所がいくつかあります。さらに、事実として間違っている表現をしている部分もあります。
それは、StoryHubは、独立したスタートアップ企業が開発したAIツールであるにもかかわらず、朝日新聞が自社で開発したものだと紹介してしまっている点です。
実は「StoryHubは朝日新聞以外の会社が開発したツールである」ということは、当然すぎるほど当然の前提だったため、メモの中ではそのことを記していませんでした。しかし、NotebookLMはその前提を知らなかったため、このような勘違いをしてしまったというわけです。
ポッドキャストと文字起こしを公開
以上のように不正確な点がいくつかあるポッドキャストですが、語られている内容はおおむね正しいといえます。また、AIパーソナリティーは角田社長の発言に対して、示唆に富む指摘をしています。
全体として聴いてみると、「AI時代のメディアの役割」を考えるうえで、なかなか悪くない素材になっていると感じました。
そこで、上記のような注釈をつけた上で、公開することにしました。
また、「ポッドキャストを聴いている時間がもったいない」という人のために、その内容を文字起こしした対談記事を以下にまとめてみました。
こちらの文字起こしでは、おかしな表現は適切なものに修正しています。そして、StoryHubをめぐる「勘違い」についても、該当箇所で詳しく説明するようにしました。
ぜひ、時間のあるときに、ポッドキャストを聴くか、対談記事を読んでもらえると嬉しいです。
「メディアとAI」をテーマにしたオンライントーク
なお、10月31日(金)21時から、あしたメディア研究会の企画として、「メディアとAI」をめぐるニュースについて考えるオンライントークを開催します。
その中で、朝日新聞の角田社長のセッションに対する感想も話したいと思います。興味がある方は、以下のページをご確認ください。
生成AIは「かなりのヤバさ」がある
アサコ: こんにちは。生成AI、ほんとにものすごい勢いですよね。これが、私たちの情報との関わり方、特にニュースのような信頼性がすごく求められる分野をどう変えていくのか。今回は、まさにその渦中にいる伝統的なメディア、朝日新聞社のトップ、角田(つのだ)社長がテレビプロデューサーの河瀬さんと語り合った対談記録がありまして、これを元に、最前線の葛藤とか戦略に深く迫ってみたいと思います。
手元にあるのが、その資料ですね。老舗メディアのトップがこのAIの波をどう見て、どう乗り越えようとしているのか。言葉からは強い危機感と未来への大胆な賭けみたいなものもちょっと感じられますよね。
今回のテーマは、伝統メディアはAIというこの破壊的な技術とどう向き合って、真っ当な情報流通、この使命を守り抜けるのか。こんな感じでしょうか。さっそく、角田社長が感じているというAIに対する切迫した危機感、ここから見ていきましょう。
ジツオ: まさにそこが全ての出発点ですね。資料を読むと、角田社長、生成AIについてかなりの「ヤバさ」があると。これ、非常に率直な言葉で表現していますよね。
アサコ: 「ヤバさ」ですか。
ジツオ: ええ。手間暇かけて取材して、裏付け取って記事にする。このプロセス自体がAIによって根底から揺さぶられるかもしれないと、そういう認識なんです。実際に朝日新聞と日本経済新聞が、記事を学習データに使われたとして、AIサービスのパープレキシティを提訴したという動きもありました。これも、その危機感の表れでしょうね。
アサコ: なるほど。単なる著作権侵害とか、そういうレベルの話じゃない。もっと大きな問題意識があるということですね。
ジツオ: その通りです。彼が使っている「真っ当な情報流通の制空権」。
アサコ:制空権?
ジツオ:ええ。これがそれを象徴していますね。制空権、つまり空を支配する権利、これは情報が飛び交う空間の主導権をプラットフォームとかAIに握られちゃうんじゃないか、という強い恐れを示唆しているんです。
アサコ: 単に自社のコンテンツを守るということ以上に、信頼できる情報がちゃんと人々に届く社会、そのインフラ自体が危うくなるんじゃないという懸念ですね。次世代に、責任ある情報空間を残せるのかというメディアとしての使命感もすごく強くにじみ出ています。企業経営という枠を超えた社会的な課題として捉えてるんですね。
ヤフーに「制空権」を握られた苦い過去
ジツオ: その強い危機感の背景には、やっぱり過去の苦い経験もあるみたいですね。1996年にウェブサイトのアサヒコムを立ち上げた時の反省点に触れてる部分がありました。
アサコ: ええ。当時は良いコンテンツを作ることにこう目が行きがちで、それをどうやって読者に届けるか、つまり流通のところまで戦略が及んでなかったと。
ジツオ: そうなんです。結果的にヤフーみたいなポータルサイト、今でいうプラットフォーマーにニュース流通の主導権、つまり制空権を握られてしまって、広告収入も奪われちゃった、と。そして、本来の主力である紙媒体の読者も減り続けて、新聞協会平均で年間7.5パーセント減という数字も出ていましたね。
アサコ: 年間7.5パーセント減。それはかなり衝撃的ですね。
ジツオ: そうなんです。このインターネット黎明期の経験が、ある種のトラウマみたいになってるのかもしれませんね。だからこそ、AIに対してもまた同じ轍を踏んではいけないという思いがすごく強いんでしょうね。
アサコ: ただ、その過去の経験則だけでは、ちょっと捉えきれないのが、今回のAIの進化のスピード感ですよね。対談相手の河瀬さんも指摘していますけど、この加速度が尋常じゃない、と。
ジツオ: まさにそこが過去との大きな違いですね。ChatGPT4が出て、その能力に世界中が驚いてから、ほんの短い期間で、今度はSORA2みたいな、まるで実写と思うような動画を生成するAIが出てきた。
アサコ: うーん、確かに。
ジツオ: この進化の速さを見ると、インターネットが普及したときのペースとは、もう比較にならないですよね。だから、過去の成功体験とか失敗体験が、必ずしも未来への有効な羅針盤になるとは限らない、という厳しい現実認識があるようです。だからこそ、単なる警戒だけじゃなくて、もっと踏み込んだ対応が必要なんだ、と。
「AIに全振り」宣言と「AI委員会」
アサコ: その危機感とスピード感の中で、角田社長自身のAIに対する認識もかなり大きく変わっていったという経緯が語られてますね。2022年末にChatGPTが登場した当初は、正直1年くらいあまりピンときてなかった、と。これはちょっと意外でした。
ジツオ: トップ自身も最初は様子見だったというのは、興味深い告白ですよね。でも、その後のAIの目覚ましい進化を目の前にして、さらにDeNA(会長)の南場智子さんの話とか、あと外部のコンサルタントから「これからの時代、AIを使える社員を育てるのは社長の義務だ」というかなり強い言葉があったみたいで。
アサコ: 「社長の義務」ですか。
ジツオ: ええ。それで背中を押されたと。そして「AIに全振りする」というかなり大胆な宣言に至るわけです。これは歴史ある大企業にとっては相当な覚悟とエネルギーが必要な決断だったはずですよね。
アサコ: 全振りですか。いやあ、社内からの反発とか戸惑いも当然あったでしょうね。
ジツオ: もちろんあった、と率直に認めてますね。心理的な抵抗という言葉を使っています。長年のやり方を変えることへの抵抗感というのは、どんな組織にもありますからね。
アサコ:ええ。
ジツオ:だからこそ、トップダウンで強い姿勢を示す必要があったんでしょう。社長自らが「AI委員会」の委員長に就任して、さらに「AIエバンジェリスト」っていう役割を社内で公募したそうです。定員50人のところに88人も応募があった、と。特にアンダー30、つまり30歳以下の若手社員からの反応がすごく良かったというのは、注目すべき点ですね。
アサコ: 若い世代はもう、AIが身近なツールとして存在してるのが当たり前なのかもしれないですね。
ジツオ: そういうことでしょうね。大学のレポート作成なんかで、普通にAIを使いこなしてる世代が入社してきているわけですから、彼らにとってはAI活用は抵抗どころか、むしろ自然な流れというか。トップの本気度と現場の若い世代からの突き上げ、この両方が組み合わさることで、ようやく組織全体に変革の機運、モメンタムってやつですかね、それが生まれてくるということなのかもしれません。トップのコミットメントだけでは、なかなか巨大な組織って動きませんからね。
人間は「人間にしかできないこと」に集中
アサコ: では、その「AI全振り宣言」のもとで、具体的にAIをどう活用しようとしているんでしょうか。資料では、大きく2つの狙いが語られていましたね。「業務の効率化」と「新しい価値の創造」。
ジツオ: ええ。まず効率化の例として挙がっているのが、科学技術担当の記者が大量の学術論文を読む際に、AIに要約させて、まず全体像とかポイントを掴むという使い方ですね。なるほど、これによって記者はより本質的な取材活動、つまり関係者へのインタビューとか深掘り分析とか、そういうところに時間を集中できるというわけです。
アサコ: なるほど。AIが得意な情報処理は任せて、人間は人間にしかできないことに集中するということですね。
ジツオ:ここで重要なのが、角田社長が「人間中心」という点をすごく強調していることです。
アサコ:人間中心?
ジツオ: ええ。AIはあくまでツールであって、最終的な判断とか価値創造は人間がやるんだというスタンスです。そして、効率化と並んで重視されているのが新しい価値をどう作るか。これは報道機関としてのまさに根幹に関わる問いですよね。
アサコ:うんうん。
ジツオ:AI時代にジャーナリズムの価値をどう再定義して、高めていくのか。その中で人間が長年培ってきた専門知識とか取材力、経験に基づく勘みたいな、いわゆる「暗黙知」。これは言葉で説明しにくい、経験に裏打ちされた知識とかスキルのことですが、この部分をどう活用してAIと組み合わせるか。それが鍵になると考えているようです。
アサコ: ただ、その効率化を追求するあまり、取材とか確認がちょっとおろそかになったりしないのかなという懸念も少し感じますけど。
ジツオ: それは非常に重要な指摘ですね。角田社長もその点は意識していて、AI利用で万が一、間違いとか不適切な表現があれば、それも包み隠さず公表すると明言しています。
アサコ: ほう。
ジツオ:これは報道機関としての信頼性を維持するための覚悟の表れでしょうね。効率化と品質担保のバランスをどう取るか、これは常に問われ続ける課題ですね。AIを使うからこそ、より一層のファクトチェックとか倫理的な配慮が求められるとも言えるかもしれません。
「スーパージャーナリスト」構想
アサコ: そして話は未来へと進んでいくわけですが、ここが今回の対談で、もしかしたら最もインパクトのある部分かもしれないですね。「10年後、15年後には、一般的な新聞記者はいなくなると思う」という、かなり衝撃的な予測をしています。
ジツオ: これは最初に読んだとき、私も「えっ?」と思いましたね。かなり大胆な発言です。現在の一般的な記者の仕事、例えば定型的な発表記事の作成とか、既知の情報をまとめるような作業はAIに代替されていくだろう、と。そういう見立てですね。
アサコ: その代わりに、どんな人材が必要になると考えているんでしょうか。
ジツオ: 彼が提示しているのが「スーパージャーナリスト」というコンセプトなんです。
アサコ: スーパージャーナリスト?
ジツオ: ええ。特定の分野、例えば、政治、経済、科学、国際情勢とか、そういうことについて極めて深い専門知識と洞察力を持っていて、なおかつ、速報性も兼ね備えている人材。第一報はSNSなんかで素早くキャッチしつつ、そこからわずか1、2時間で、背景にある文脈とか多角的な分析まで含めた100から200行程度の質の高い記事を書き上げられる。
アサコ: 1、2時間で?
ジツオ: ええ。そんな能力を持ったジャーナリストが各分野に合計で100人から200人いれば、報道機関として十分に機能するんじゃないか、と。これは現在の記者数からすると、10分の1程度の規模感ですね。
アサコ: 100人から200人のスーパージャーナリスト、それだけで多様なニュースとか社会の出来事を網羅できるものなんですかね? 例えば、地域密着の取材とか、あとはニッチだけど重要な問題への目配りとか、そういう点はどうなるのかなって、ちょっと疑問も感じますけど。
ジツオ: それはまさに、この構想の核心的な問いですよね。このスーパージャーナリスト像が示唆しているのは、AI時代におけるジャーナリズムの価値が、より深さと速さ、そして独自性にシフトしていくということだと思うんです。
アサコ: 深さ、速さ、独自性。
ジツオ: ええ。つまり、誰もがアクセスできる情報の要約とか定型的な報道はAIに任せて、人間はAIには真似できない一次情報へのアクセス能力、独自の取材網とか情報源ですよね。それと深い洞察に基づく迅速な分析力、解説力。これで勝負するんだという戦略です。ただ、ご指摘の通り、網羅性とか多様性という点では、課題が残る可能性はありますよね。
おそらく、この少数のスーパージャーナリストを、AIとかデータ分析ツール、そしてサポート人材が強力にバックアップする体制を想定しているんでしょう。深掘りすべきニュースと、AIで効率的にカバーできるニュースの住み分けが進むのかもしれません。
これは他の専門職、例えば、弁護士さんとか会計士さんとか、そういう分野でもAIによって仕事の内容が変わっていくのとちょっと似た構造かもしれないですね。定型業務はAIへ、高度な専門判断とか対人スキルが求められる領域は人間へ、という流れですね。
AIを活用した効率化の具体例
アサコ: なるほど。そのスーパージャーナリストを支える技術的な基盤も重要になってきますよね。自社で開発しているStoryHubというシステムの話が出てきました。
(注)実際は朝日新聞の開発ではなく、外部のスタートアップ企業「StoryHub」が開発したAI編集支援システム。この箇所は、Google NotebookLMが事実誤認してしまっている。いわゆる「ハルシネーション」が起きている。ただ、その原因は「人間がまとめたメモにそこまでの説明がなかったから」とも言える。つまり、人間の説明不足が招いた嘘と考えられる。
ジツオ: ええ。これが変革のエンジンになるという位置づけのようです。単に外部のAIツールを使うだけじゃなくて、自社の業務プロセスとか報道の特性に合わせて最適化された技術基盤を持つことが重要だという考えですね。
(注)この箇所も「自社開発したAIツール」という認識を前提にした記述なので、不正確な解釈と言える。
ジツオ:ここで強調されているのは、このStoryHubの開発メンバーが単なるIT技術者じゃなくて、コンテンツ、つまり報道そのものに深い関心を持ってる人たちだという点なんです。
アサコ: それは大きいですね。
ジツオ: ええ。技術が目的化するんじゃなくて、あくまでジャーナリズムの質を高めるためのツールとして開発されているんだ、と。
アサコ: 具体的にはどんなことができるシステムなんでしょう?
ジツオ: いくつか例が挙げられていましたね。例えば、シンポジウムとか記者会見の内容をリアルタイムでテキスト化して、AIが要点を抽出して、記事の骨子案を作るみたいな支援。これで記者はより早く、より深く、分析的な記事作成に集中できる、と。
アサコ:ふーん。
ジツオ:あるいは、人手が不足しがちな地方支局では、ファクスで送られてくる大量のプレスリリースなんかをAIが自然言語処理(NLP)技術を使って読み取って、「殺人」とか「汚職」とか、事前に設定された重要キーワードを検知すると、自動で担当記者にアラート通知を送る仕組み。
アサコ: へー。それは便利そう。
ジツオ: これによって、従来は見過ごされていたかもしれない可能性の端緒をつかみやすくなる、と。ほかにも、子ども向けの教育事業でAIを使って学習レベルに合わせた問題をつくるとか、報道以外の分野でも活用が進んでいるようです。
アサコ: しかも、その技術とかノウハウを自社だけで囲い込むんじゃなくて、他社とも共有していくっていう姿勢を見せてるのがちょっと興味深いですよね。真っ当な情報流通社会という大きな目標のためには、いいところは見せ合っていくべきだと。
(注)プレスリリースの自動読み取りや教育関連事業での活用は、StoryHubではなく、朝日新聞の技術部門による開発とみられるので、ここの表現は間違っていないといえそうだが、普通に読むと「StoryHub事業」による成果ともみえるので、問題がないわけではない。
ジツオ: ここは、非常に重要なポイントだと思います。ともすれば、AI活用って、自社の競争力強化とかコスト削減とか、そういう側面ばかりが注目されがちですけど、角田社長は業界全体、ひいては社会全体の情報流通の健全性をどう保つかという視点を持っているんですね。
アサコ:うーん。
ジツオ:特にフェイクニュースとか誤情報が、AIによって拡散しやすくなる懸念がある中で、信頼できる情報を提供するための技術とかノウハウは、ある程度オープンにして、業界全体のレベルアップを図るべきだという考え方なんでしょう。もちろん競争領域はありますが、社会インフラとしての報道を守るためには協調も不可欠だ、と。自社の技術基盤「StoryHub」を持ちつつも、他社と連携していくというバランス感覚がうかがえますね。
(注)この箇所も「StoryHubは、朝日新聞が自社開発したAIツール」という認識を前提にした記述なので、間違っている。
AI時代のオールドメディアの役割とは?
アサコ: そうした技術と人材戦略の先に、どんな未来を描いているんでしょうか。