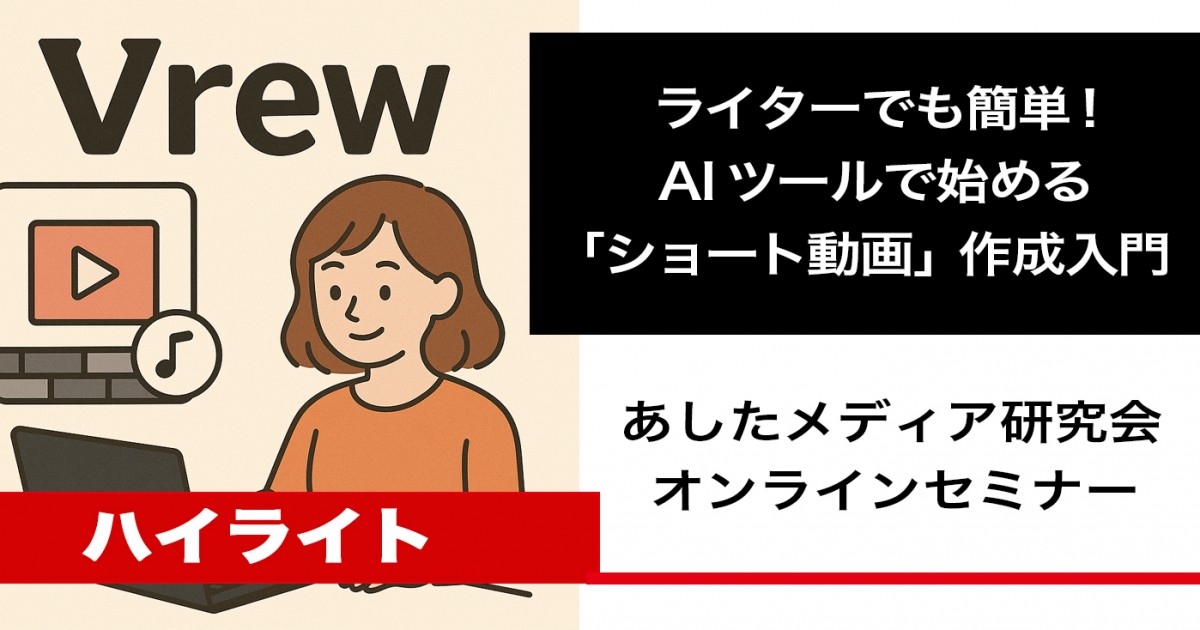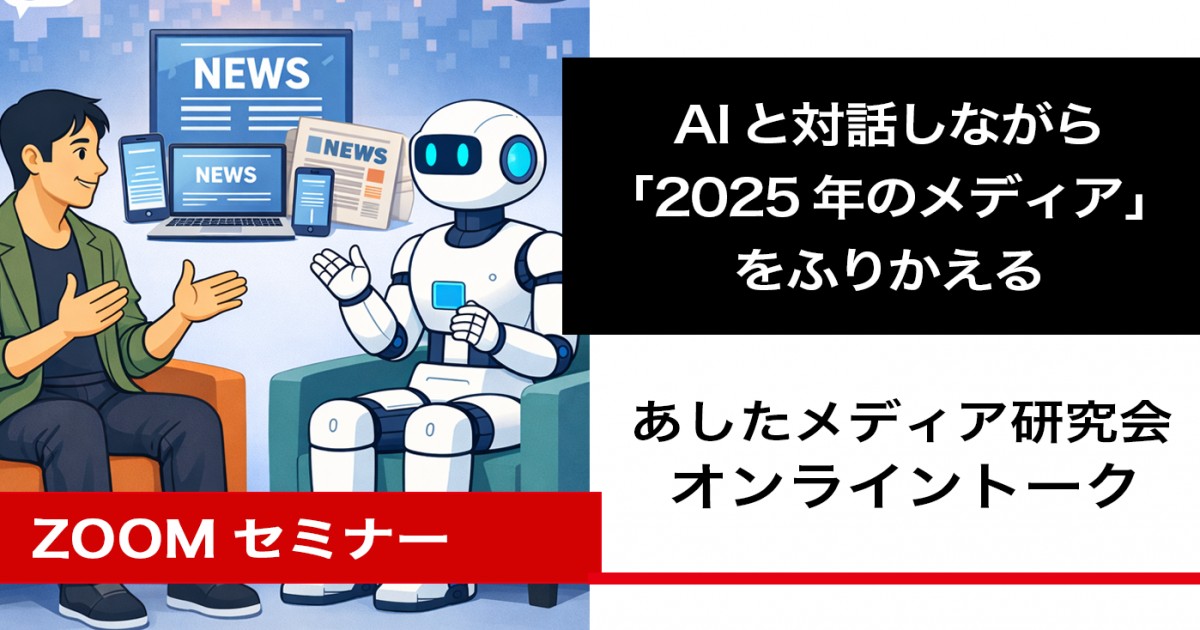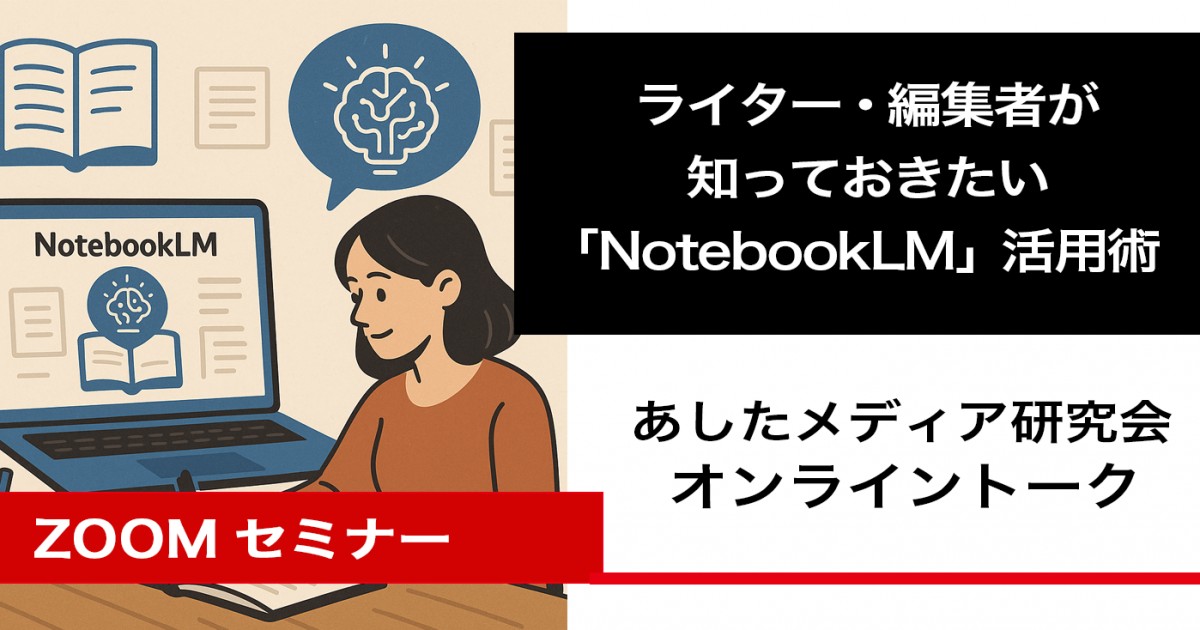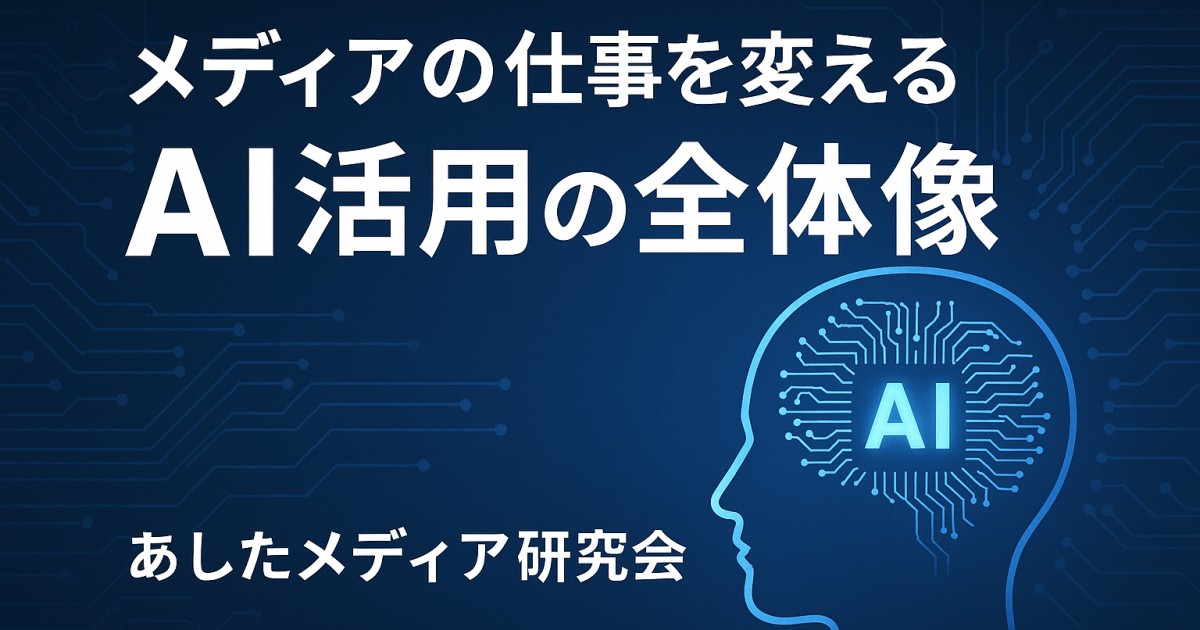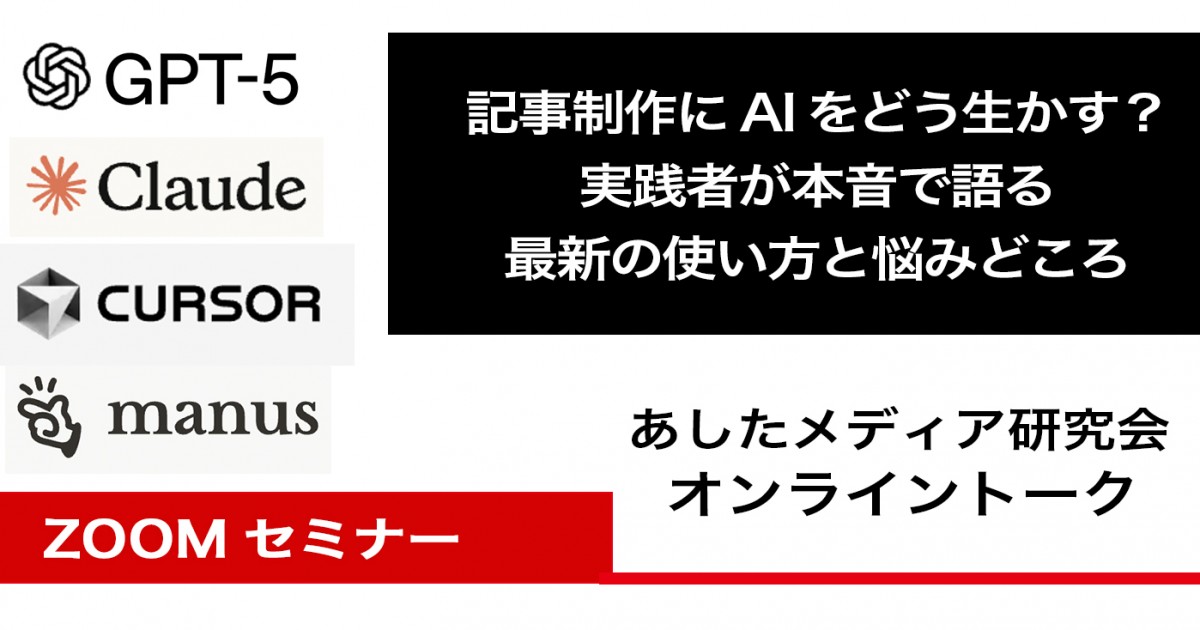「コンテンツを作るのも見るのもAI」時代のメディアはどう変わる?

「AIが人間の代わりにニュース記事を読んで、ポイントを人間に教えている」というイメージのイラスト。ChatGPTに描いてもらった
ストレートニュースの価値がゼロになる!?
「ストレートニュースの価値はゼロになる」。そんな刺激的なタイトルが目を引くイベントレポート記事が3月末、Media Innovationに掲載されました。note CXOの深津貴之さんは、カンファレンスの場でこう語りました。
「ストレートニュースの価値は今後ゼロに近づく」
もちろん、明日いきなり価値がゼロになるわけではありません。しかし、AIの進化やSNSの普及により、記者がストレートニュース(事実を簡潔に伝える一次報道)を伝えるだけでよかった時代は、過去のものとなりつつあります。
問題は、記事を書く側だけでなく、読む側の行動も変わろうとしていることです。深津さんは、コンテンツの“送り手”と“受け手”の両方に起こる変化を、次のように語っています。
AIの活用で記事作成速度が上がると今よりもコンテンツがあふれかえるので、読者もAIで興味を持てそうなコンテンツを絞り込むようになる可能性があります。コンテンツを作るのも見るのもほとんどAIで、人間が見るのは上澄みの1%だけ。そんな世界がくる……とまでは断言できませんが、そうなってしまった場合に備える必要はあると思います。
ここで語られているのは、「コンテンツの洪水」を処理するのはAIであり、人間が直接触れるのはそのごく一部になるという未来です。
このような構造変化の兆しは、すでに現れています。
AIが「読む」時代のニュースメディアとは?
たとえば、最近急速に存在感を増しているリサーチAI「Perplexity」。このAIは、ウェブ上の信頼できそうな情報源を参照しながら、人間の質問に答えてくれます。
「今度、半導体の展示会に行くから、関連ニュースをざっと教えて」と尋ねると、たちどころに注目すべきトピックとそのソースを一覧で提示してくれます。特に、自分の専門外の領域を“速く”“ざっくり”把握したいときには大いに力を発揮します。
さらに、Perplexityには「発見(ディスカバー)」というコーナーがあり、世界中のホットトピックがまとめられて更新されます(現在はアメリカ中心ですが、今後の日本対応も期待されます)。

もはや人間がひとつひとつニュースを見て比較・選別するのではなく、「まずAIが読み、人間はそのエッセンスだけを見る」という構造が現実になりつつあります。
このような「ニュース・キュレーション」の役割は、Yahoo!ニュースやLINEニュースといったニュースポータルや、Googleの検索窓の下に表示される記事一覧(=ディスカバー)が果たしてきた機能と似ています。
Perplexityは、ニュース・キュレーションの新たな選択肢となりうるのかもしれません。
「AIをまったく触らない状況は、すぐになくすべき」
こうした環境変化の中で、メディアの仕事に関わる人間がすべきことは何でしょうか?