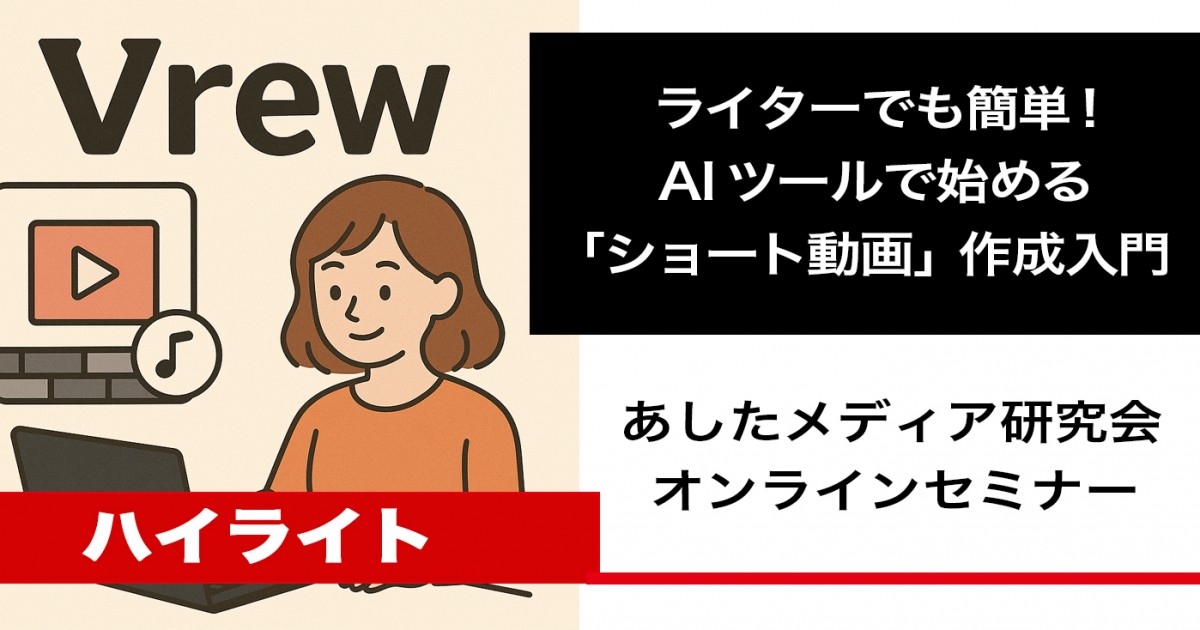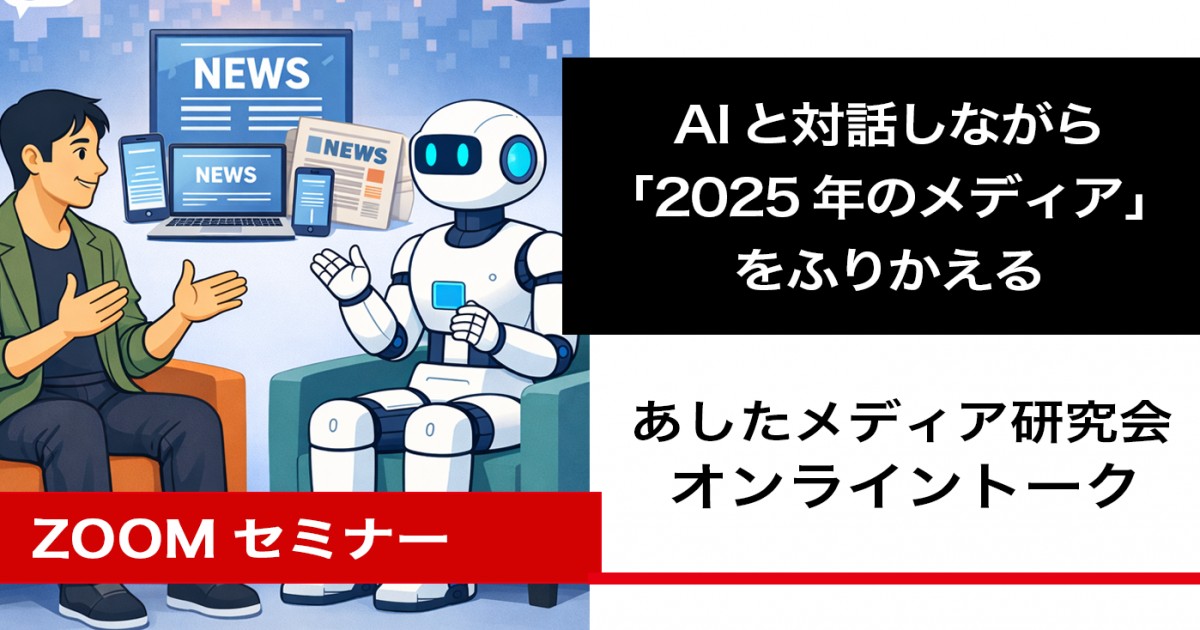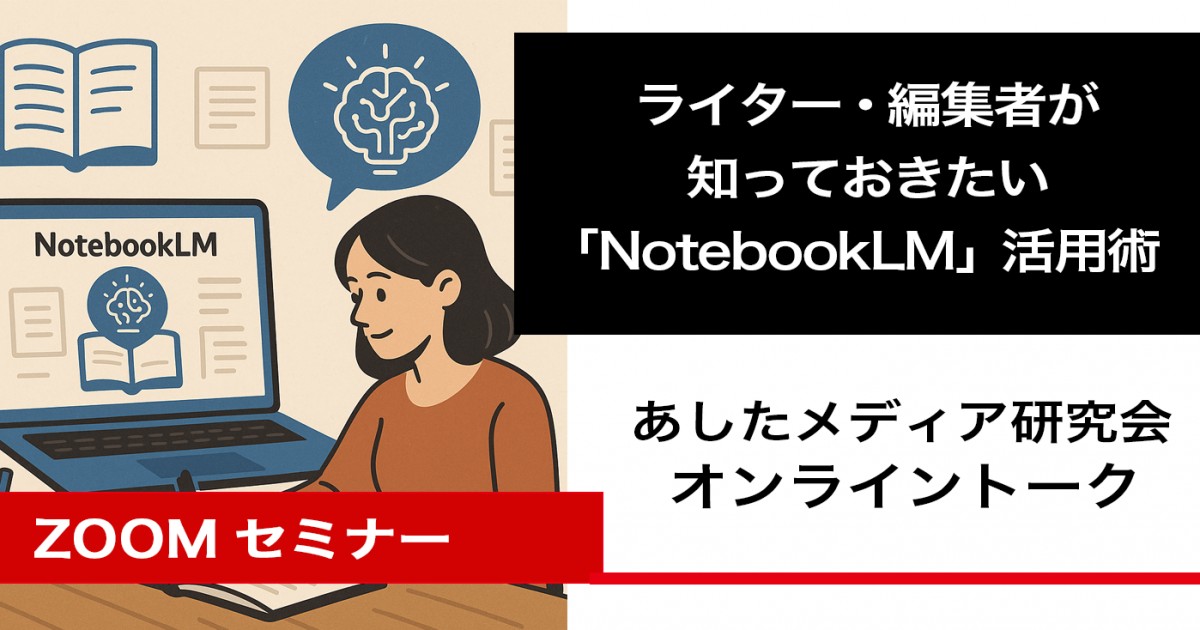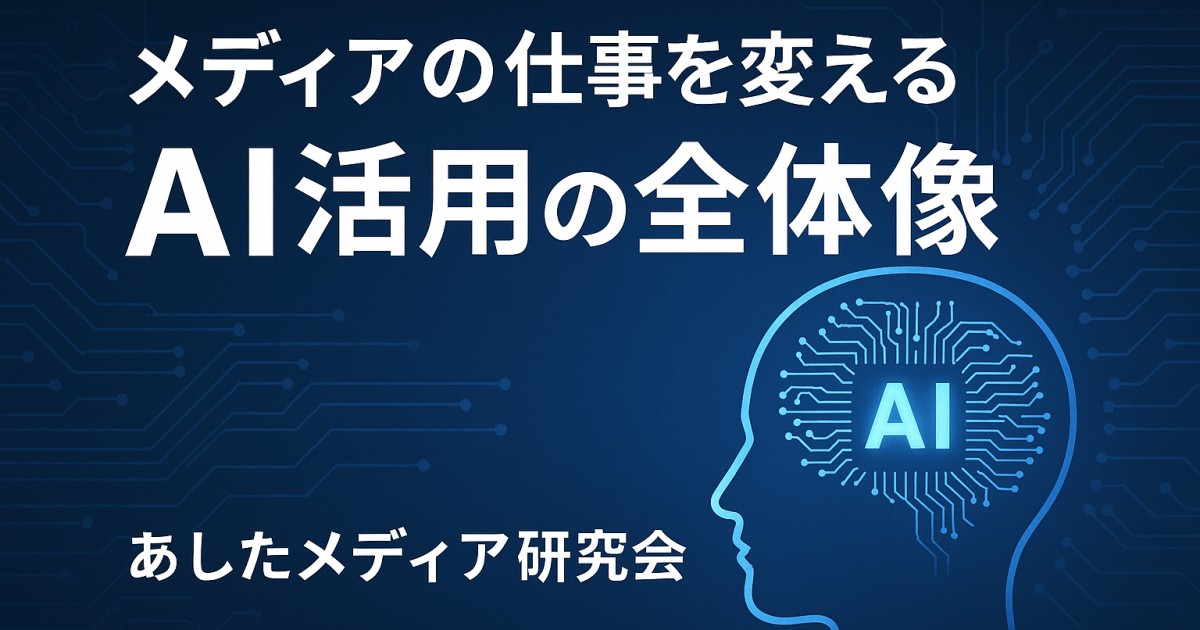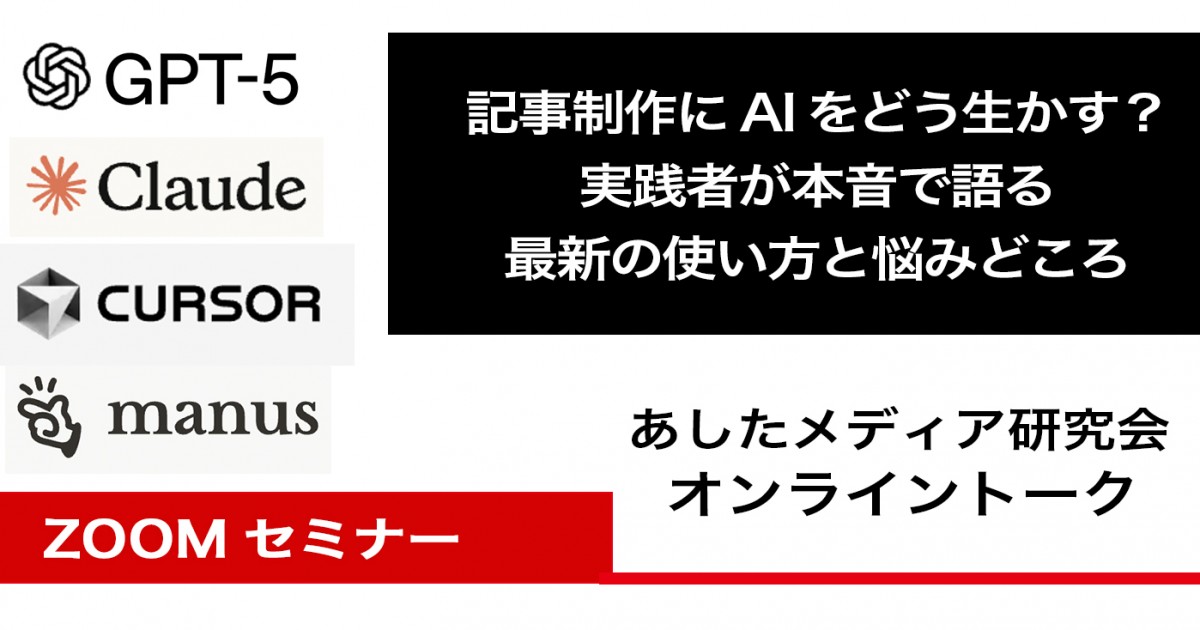「鳥の言葉」が解き明かす新たな言語学の世界
ひらばやし:動物言語学者の鈴木先生が、シジュウカラの言葉の研究を続けてきた歴史が中心となっています。今年1月に発売されたばかりなのに、3月後半の時点ですでに5刷。Amazonでの紹介によると、8万部も売れているんです。
――すごい反響ですね。具体的には、どんなことが書かれているんですか。
ひらばやし:大学時代、1泊500円の山荘にこもって研究していた話から始まり、その研究成果が評価されて、次のテーマへと進んでいく過程が描かれています。研究内容としては、シジュウカラが文法を使って文を作れることが大きなテーマです。そのほか、ジェスチャーによるコミュニケーションや、他の種類の鳥とも言葉が通じているという発見も紹介されています。
――本のタイトルに「鳥の言葉がわかる」とありますが、本当なのでしょうか。
ひらばやし:はい、鈴木先生は「鳥の言葉」が理解できます。シジュウカラが「タカが来た」「ここにエサがある」と言っているのがわかるんです。さらに、NHKの科学番組「ダーウィンが来た!」の収録中に、スタッフも鳥の言葉がわかるようになったという話も出てきます。
「人間だけが特別」という思い込みへの挑戦
――「動物言語学」というのは新しい学問分野のようですね。
ひらばやし:そうですね。従来の言語学では「言葉を使えるのは人間だけ」と考えられてきました。鈴木先生はそれに疑問を持ち、「鳥も言葉を話せる」ことを証明しようとしたんです。最初に「鳥も単語がわかる」と発表し、「文も作れる」「文法を理解している」と証明していく過程が、本の大きなストーリーです。
――興味深い展開ですね。
ひらばやし:鈴木先生は、「言葉を使うのは人間だけ」という見方は、人間が他の動物より優れているという誤った認識だと考えています。人間も動物の一種で、人間の言葉も動物の言葉の一種だというフラットな世界観を持つべきだ、と。これまでの動物生態学でも単語レベルの研究はありましたが、厳密な実験で証明した例は少なかったそうです。鈴木先生は、この「動物言語学」を他の動物にも広げようと取り組んでいます。
理系出身ライターの目に映る「研究の魅力」
――この本の魅力は、どこにあると感じますか。
ひらばやし:鈴木先生の発見ももちろん興味深いですが、この本の特徴は「研究のプロセス」の面白さです。仮説を立てて検証していく過程は「探偵業」のような側面があり、それが非常に魅力的。また、科学を「わかりやすく、面白く」伝える工夫が詰まっていて、ライターとしても勉強になりました。
――ひらばやしさんは現在、どんな活動をしているのでしょう?
ひらばやし:IT企業で研究職や新規事業の立ち上げ、広報・宣伝を経験した後、7年前にフリーランスになりました。2年半ほど前から大学の先生の研究を高校生に伝えるメディアの仕事をするようになり、それが自分に合っていると感じました。現在は、大学の研究紹介や企業の技術事例など、理系関連の仕事が7〜8割を占めています。
科学は読まれているのに、なぜ理解が広がらないのか
――大学の専門的な研究を高校生に伝えるのは大変そうですね。
ひらばやし:高校生向けの記事は、教科書から高校生が持っている知識を予測できるので、一般向けよりもターゲットが絞りやすい面はあります。ただ、大学の修士課程レベルでないと理解が難しい最先端の研究内容をどう伝えるかは工夫が必要です。さらに、媒体によっては図や数式が使えないので、例えば、幾何学の面白さを文章だけで表現しなければいけません。そんな難しさもあります。
――メディアに関わる立場として、気になっていることはありますか。
ひらばやし:『僕には鳥の言葉がわかる』がこれだけ売れ、数学関係の本もAmazonのランキング上位に入るなど、科学系コンテンツは注目されているはずです。でも不思議なことに、科学技術への理解が社会で深まっているようには見えません。この矛盾が気になっています。科学技術への関心を広げ、特に基礎研究者が活動しやすい環境を作るために、自分に何ができるか考え始めているところです。
※この記事は、あしたメディア研究会のポッドキャスト「メディアびとブックトーク」の内容をもとに作成しました。
すでに登録済みの方は こちら