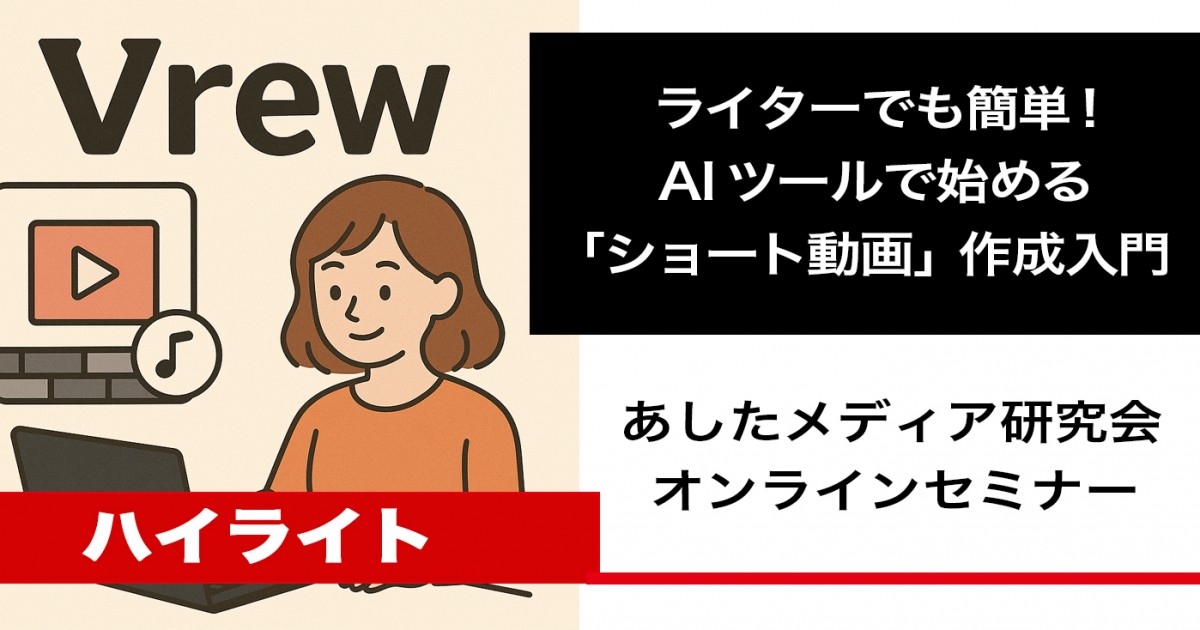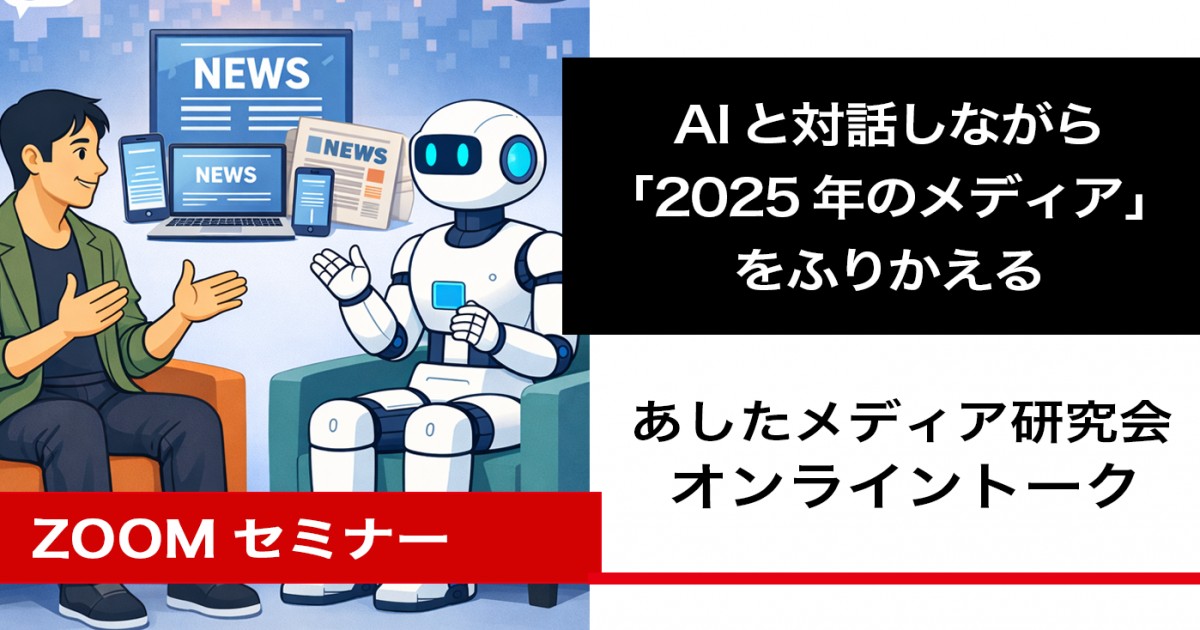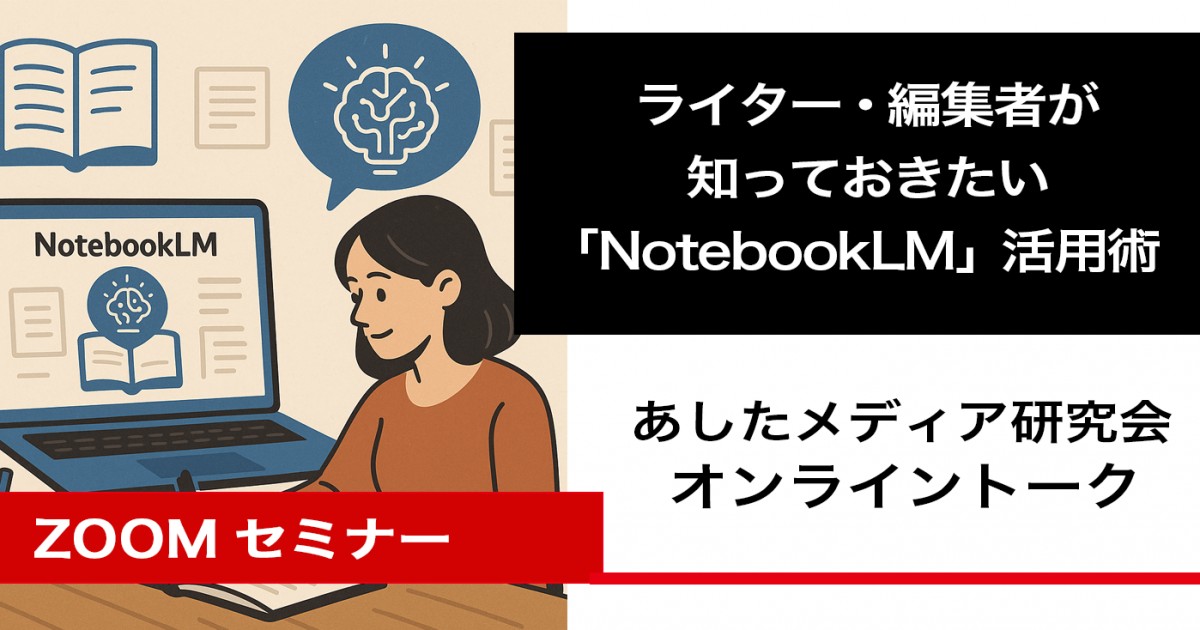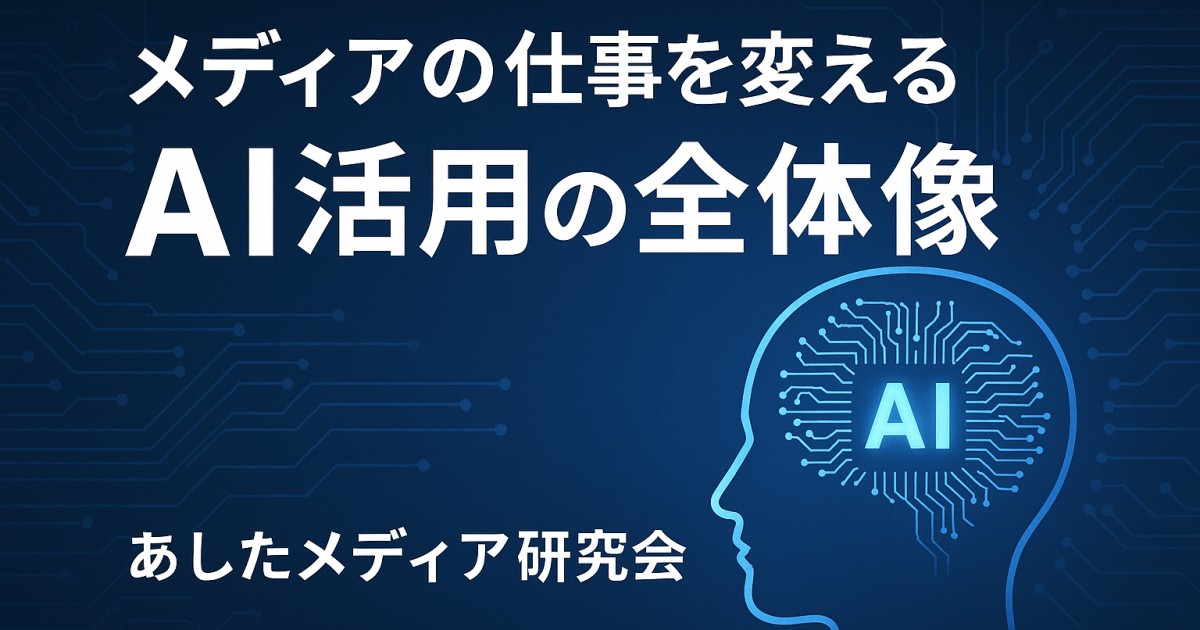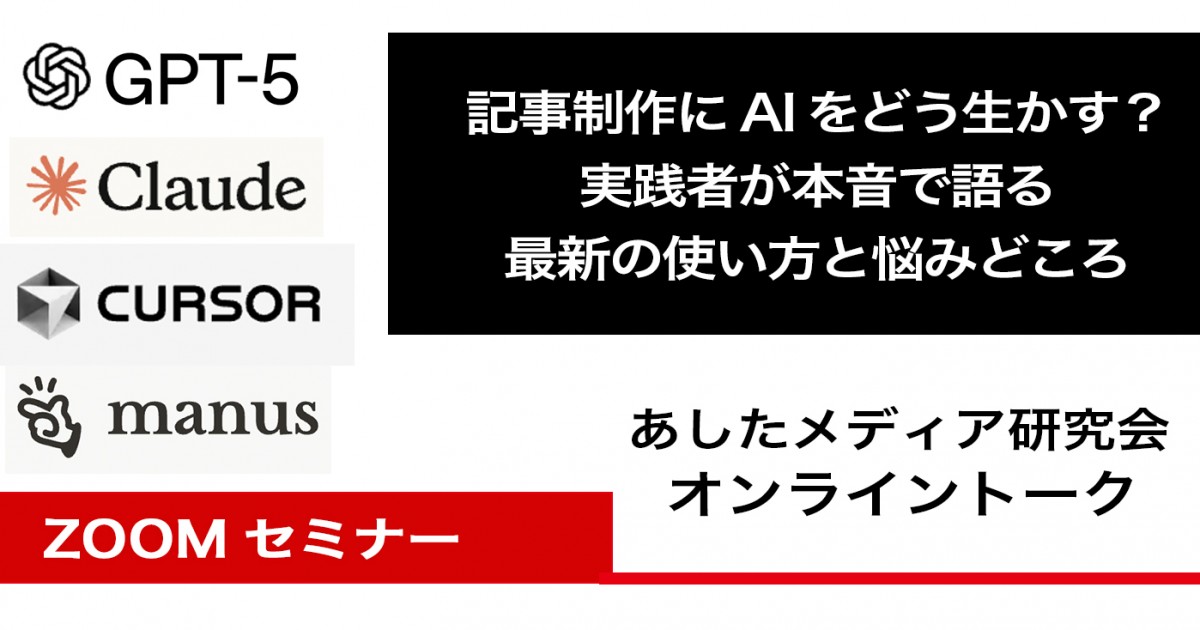新聞記者のネガティブなイメージを変えるには?
こんにちは。あしたメディア研究会の亀松です。
僕は、2019年4月から関西大学総合情報学部の特任教授として「ネットジャーナリズム論」という授業を担当しています。ネット時代のジャーナリズムに関する基本的な知識を伝え、「どのようにニュースに接していけばいいか」を学生自身に考えてもらう授業です。
この授業では、複数のメディア関係者にゲストとして登壇してもらい、メディアの現場体験を学生に向けて語ってもらっています。そのうちの一人が、京都新聞の記者・八幡一男(やはた・かずお)さん。「新聞記者のリアル」と題して、事件や災害の取材体験を話してもらうのですが、これがとにかく好評なのです。

授業後にアンケートを取ると、「新聞記者に対するイメージが良い方向に大きく変わった」という感想が多数寄せられました。
「新聞記者のイメージがガラッと変わった」
「自分自身の新聞記者のイメージとしては、決して良いイメージはありませんでした。モラルのない行為をしていると身勝手に考えていました。現実は、しっかりと取材対象と向き合い仕事を真摯に取り組んでいるのだと感じました」
「私が持っていた新聞記者のイメージは、立場が上の方が定めた内容に沿うように、事実でも事実でなくても書くといったあまりよくないイメージでした。しかし八幡一男さんの『自分の目や耳で得たことを信じる』という言葉に、自分がどれだけ勝手なイメージを持っていたのかと感じ、反省しました」